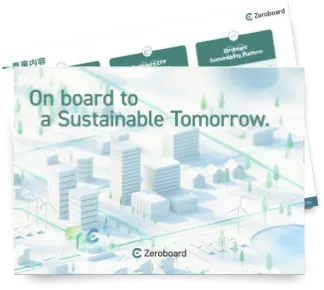インフロニア・ホールディングスが、SBTを取得しCDPスコアも向上 ――気候変動対策とビジネスのサステナブルな成長を両立する取り組みとは?


インフロニア・ホールディングスが、SBTを取得しCDPスコアも向上 ――気候変動対策とビジネスのサステナブルな成長を両立する取り組みとは?
お話をうかがった方(部署・肩書は取材時)
経営戦略部サステナビリティ推進室
林 昌明 様
加藤 慈子 様
サステナビリティ目標達成に向けた取り組みの一環として、国際的な認証取得を目指す企業が増えています。その一つが、パリ協定の目標に整合した、科学的根拠に基づく温室効果ガス(GHG)削減目標の設定を国際的なイニシアチブであるScience Based Targets initiative(SBTi)が検証・認定するSBT(Science Based Targets)です。しかしSBTの申請にあたっては英語や専門知識が必要なこともあり、初めて取り組む企業や担当者は苦労することが多いのが実情です。今回はSBT認定取得のためにゼロボードのコンサルティングサービスを利用されたインフロニア・ホールディングス株式会社様に利用の決め手や効果、今後のサステナビリティへの取り組みについて伺いました。
-
課題・背景
- 気候変動対策を深化させるため、説得力のある目標を社内外に提示したかった
- SBTを取得するための専門知識とサポートが必要だった
- GHG排出量算定システムの導入を検討していた
-
ゼロボードに決めた理由
- 納得感のあるコストおよびSBT申請に関する専門性と充分な支援実績
- ゼネコン業界に対する豊富な知見
- 企業としての信頼性
-
導入後の効果
- SBT事務局との適時・適切なコミュニケーション・回答支援などによりSBT認定を取得
- CDPなど複数の環境関連のスコアが軒並みアップ
- 外部機関からの寄稿依頼増加といったPR効果
- 当社グループの事業会社との削減目標の目線合わせ
気候変動対策への対応を深化させるためSBT認証を取得へ
──貴社の事業内容とお二人の部署について教えてください。
加藤慈子 様(以下、加藤様):インフロニア・ホールディングス(以下、インフロニア)は2021年10月に前田建設、前田道路、前田製作所の共同持株会社として設立し、2024年には日本風力開発が加わり、主要事業会社4社でグループを構成しています。私たちインフロニアは、インフラとインフラサービスの社会課題解決に向け、「総合インフラサービス企業」として新たなビジネスモデルの実現を目指しています。建設や舗装、機械製造、再生可能エネルギー事業などさまざまなインフラ領域で事業を展開しています。さらに、上流から下流まで一気通貫でサービスを展開できる点を強みとし、企画提案や投資分野に力を入れることでインフラとサービスを通じた社会課題の解決を目指しています。
私たちは経営戦略部サステナビリティ推進室に所属し、グループ全体のサステナビリティ施策を横断的に企画、実行しています。特に私たちのチームは環境分野にフォーカスしており、再生可能エネルギーの活用や気候変動対策の推進を通じて、グループの脱炭素経営を後押しする役割を担っています。
林 昌明 様(以下、林様):2025年4月から、社内外の評価向上を目指した統合的なサステナビリティ推進体制に進化しました。環境分野の専門性に加え、統合的なサステナビリティ情報の開示や外部評価への対応にも力を入れています。
──SBT取得に取り組んだ背景や課題を教えてください。
加藤様:最大の理由は気候変動対策への対応を深化させるためです。従来、事業会社単位で進めていた環境施策をホールディングスとして一つの方針でまとめ、説得力のある目標として社内外に提示したいという意図がありました。
前田建設がSBTをすでに取得していましたが、ホールディングス体制となったことを受け、インフロニアで新たに申請する流れとなりました。ただし、英語での申請や根拠となる数値の裏付け、バウンダリーの設定といった実務面でのハードルは高く、特に過去データの収集と分類に苦労しました。
――実務上、特に苦労したポイントはどのあたりでしょうか。
林様:事業会社ごとのデータ収集が一番大変でした。30〜40社ある子会社も含めてバラバラなフォーマットを統一し、手作業でデータを集計・分析しました。統合報告書で出しているバウンダリーとの整合性も取る必要があります。加藤が実務を取り仕切って、グループ各社と細かいやり取りをしてくれました。
加藤様:グループ各社の担当者には、とても助けられました。お飾りの目標にならないよう、こまめなコミュニケーションを大切にし、一緒に議論しました。また、グループ会社との連携をさらに深め、データ集計や可視化を通じて、より実効性の高い目標管理に取り組んでいくため、GHG排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」も導入しました。
林様:ホールディングス全体での集計結果を見せたり、事業会社ごとに切り替えたり、ダッシュボードのカスタマイズ性の高さが導入にあたっての評価ポイントでした。ゼロボードに伴走支援していただきながらうまく活用していきたいと思っています。
SBTのハードルを乗り越えるには?コンサルティングサービスの重要性
──ゼロボードを選んだ理由や決め手を教えてください。
加藤様:ゼロボードとは算定システムの導入相談をきっかけに出会いました。話をする中でSBTの申請支援を行っていらっしゃることを知り、十分な専門知識があることを感じました。そのため、コンサルティングサービスを依頼する際にも安心感がありました。
自力でのSBT認定取得は難しいと考えていたので、当初からサポートしてくれる企業を探していました。ゼロボードは、支援内容に応じた適切な金額をご提示いただいたことに加え、ゼネコン企業への導入およびサポート実績を多数お持ちであることから、業界への理解が深く、私たちの事業特性に合ったサポートが期待できました。
──ゼロボードのコンサルティングサービスに対しての印象は?
加藤様:実際に英語の壁やSBT事務局とのやり取りにおいて心強いパートナーになってくださいました。単なる言葉の壁だけではなく、SBT事務局が意図していることや細かなニュアンスで分からないことがあれば気軽に相談できました。特に他社の申請時に培った知見やアドバイスは非常に助かりましたし、自分たちだけでは気付くことのできなかった解釈の違いなども認識することができました。また、時差のある海外とのやり取りでは、厳しいスケジュールを要求されることもありましたが、臨機応変に対応いただけたことに感謝しています。
SBT申請は毎年行うことではないため、専門外の企業が知見を持つことは難しいと思いますし、信頼できるパートナーとしてサポートしていただけたことがありがたかったです。
林様:ゼロボードのサポートには非常に満足しています。特にSBT事務局の細かい指摘や商習慣・文化の違いによる理解のずれを的確にサポートしてくださったのは助かりました。
――SBTの取得により、社内外でどのような変化がありましたか?
加藤様:詳細な分析はできてはおりませんが、SBT申請中の段階から気候変動情報開示のグローバルスタンダードであるCDPのスコアが2段階アップ(最高評価Aリスト)するなど、期待していた外部評価に明確な効果が現れたのは大きかったです。あらゆるステークホルダーから信頼される企業を目指すなかで、特に機関投資家に対し、私たちの取り組みを評価してもらうきっかけになったと考えています。また、社内からも一定の評価の声をもらっています。
林様:具体的な時系列としては、2024年5月にSBT申請を開始、同年9月CDP質問書への回答では「SBT申請中」と記載していました。2024年12月にSBT認定を取得し、2025年2月CDPのスコアが発表され、結果としてCDPのスコアアップにつながりました。継続的にさまざまな評価機関のアンケート対応をしてきましたが、2024年度は日経サステナブル総合調査や損害保険ジャパンESG調査、S&Pなど環境スコアが軒並みすべて上がりました。また、関連する寄稿の依頼も増え、情報発信の機会が広がり、PR効果にもつながっています。
 経営戦略部サステナビリティ推進室 林 昌明様、加藤 慈子様
経営戦略部サステナビリティ推進室 林 昌明様、加藤 慈子様
グループ横断で進める脱炭素と今後の展望
――サステナビリティに関する今後の戦略について教えてください。
林様:2025年3月に新たな中期経営計画(2025〜2027年)を発表しました。その中で、「社会課題の解決」と「企業のサステナブルな成長」の両立を目指しています。新たにグループに加わった日本風力開発と前田建設が連携し、再エネ発電所を作るなど事業の強化も進めています。Scope 1,2については自社の排出量を削減するための技術開発の機会となり、それが転じてお客様のお役に立てる可能性があります。自社の事業活動におけるCO2排出量を下げながらビジネスで利益を出し、さらに社会課題の解決へ貢献していくという二本柱です。
加藤様: 企業が事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す、国際的なイニシアチブ「RE100」達成の目標を繰り上げることを中期経営計画と共に発表しました。具体的には、2030年度までに50%、2050年度までに100%と設定していた目標を2030年度までに達成と前倒しすることにしました。再生可能エネルギーを普及させていくリーディングカンパニーとして、社会へ貢献できればと考えています。 今後、気候変動対策だけではなく環境問題対策という大きな枠で考慮する必要があると考えており、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブなどの分野にも力を入れていく予定です。それが当社のビジネスチャンスに必ずつながっていくと考えています。
――最後に、SBTを検討する他社へのアドバイスをお願いします。
加藤様:準備を含め申請には非常に時間がかかるということを念頭におき、余裕を持ったスケジュールを組むこと、そして、専門的な知識を持つコンサルティングサービスも必要不可欠だと思いました。SBT事務局からの要求・確認事項は細部にわたるため、ゼロボードの経験に基づいた的確なご対応は非常に心強く感じました。
信頼できるパートナーの協力を仰ぎ、社内での理解を深めながら、全社的な連携を大切にしていただくとスムーズに進められるのではないでしょうか。
林様:全ての元となるデータ集計の体制づくりが大切だと思います。日頃からデータを集めておくことが、スムーズな申請につながります。SBTは確かにハードルが高いですが、その先には多くの成果が待っていると実感していますので、チャレンジすることをおすすめします。
※支援内容はご契約いただくプランやオプションによって異なります。
ゼロボードではSBT申請支援のコンサルサービスを含め、お客様のニーズに合わせて、勉強会の実施や入力代行などを含め、様々なオプションのご案内も行っております。