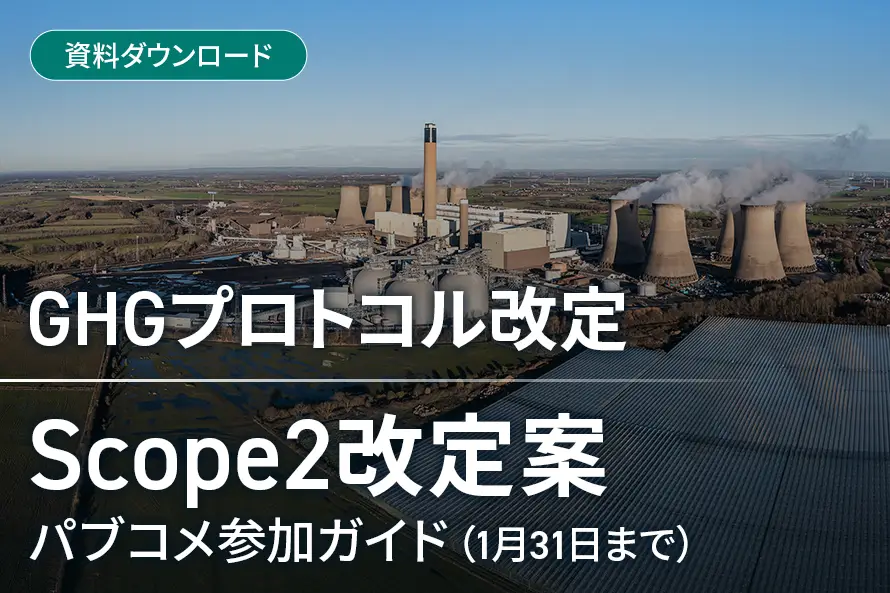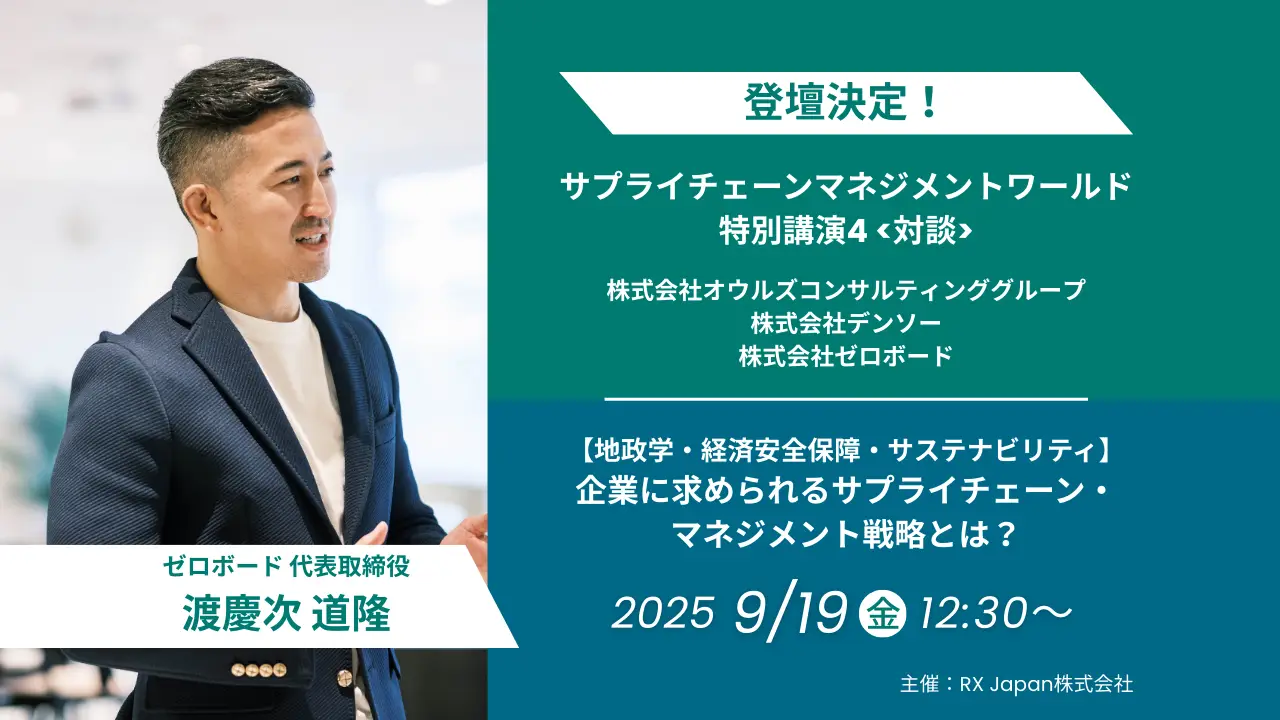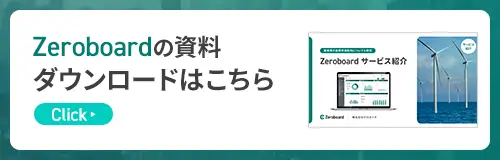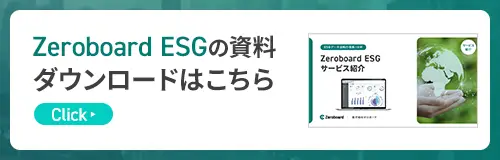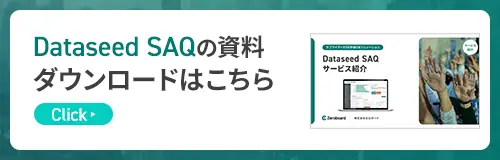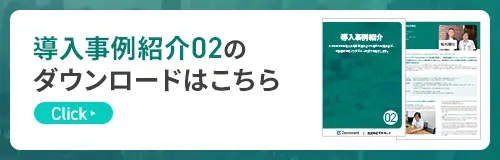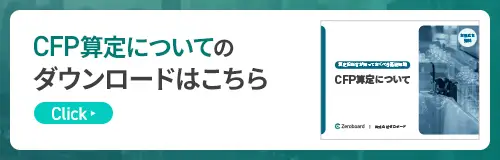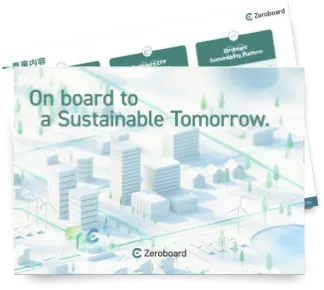迫りくる地政学リスク ― サプライチェーンへの影響と企業の備え

地政学リスクとは?その定義とサプライチェーンへの影響
地政学リスクとは、国際関係や安全保障上の緊張、国家間の対立、国内の政治的混乱などが引き金となり、経済活動やビジネス環境に重大な影響を及ぼすリスクを指します。
サプライチェーンにおいては、以下のような形で具現化します。
- 原材料や部品の供給途絶:輸出入規制や制裁により、調達が急停止する。
- 物流の停滞:港湾封鎖や航路の不安定化により、納期が読めなくなる。
- コストの高騰:輸送コストの上昇や資源価格の乱高下が利益を圧迫。
- 信用リスク:サプライヤーが規制違反や人権侵害で取引停止となる。
つまり地政学リスクは、企業のサプライチェーンそのものを揺さぶる現実的な経営リスクといえます。
近年の事例:ウクライナ侵攻・米中摩擦・中東不安
実際の事例を見てみると、その影響の大きさが理解できます。
- ウクライナ侵攻(2022年)※1
小麦・トウモロコシなど穀物輸出の停止、天然ガスの供給制限は、食品・化学・エネルギー産業に甚大な影響を及ぼしました。日本でも小麦価格が上昇し、パン・麺類メーカーが相次いで値上げに追い込まれました。 - 米中摩擦(2018年〜現在)※2
米国による中国製品への追加関税や、中国による希少金属輸出規制は、電子部品・自動車・電池産業に直接的な影響を与えました。EV用バッテリーのサプライチェーンは、中国依存度の高さが改めて浮き彫りになり、欧州・日本企業にとってはリスク分散の必要性が強調されています。 - 中東不安(2024年以降)※3
イラン・イスラエル情勢の緊迫化や紅海航路での安全確保問題は、原油・LNG輸送の安定性を脅かしています。海上輸送の遅延や保険料の高騰は、製造業だけでなく小売業にまで波及しています。
これらの事例は、地政学リスクが直接サプライチェーンリスクとして顕在化した具体例です。国家間の対立や制裁措置は単なる外交問題にとどまらず、法規制として現実のビジネス環境に組み込まれ、その結果として原材料調達の停止や物流の混乱、コストの高騰を引き起こしています。
言い換えれば、ウクライナ侵攻・米中摩擦・中東不安といった出来事は、経済安全保障の枠組みを背景に生じたサプライチェーンリスクの現れにほかなりません。
つまり、企業がこうした現象を理解し、将来に備えるためには、地政学リスクとサプライチェーンリスクを切り離さず、経済安全保障の観点から包括的に捉えることが不可欠です。
企業に求められる「リスクマネジメント」とは?
では、企業はこうしたリスクにどう備えるべきでしょうか。
国際的なリスクマネジメントの枠組み(OECDガイダンスやISO 31000など)や、各種コンサルティングファームの推奨プロセスを整理すると、企業が取るべき理想的な対応ステップはおおむね次の5段階に整理できます。
1. サプライチェーンの可視化
まずは、自社の調達網を“見える化”することが出発点です。Tier1の主要サプライヤーだけでなく、Tier2・Tier3といった下位層までマッピングすることで、どの国やどの供給層にリスクが潜んでいるのかを明確にします。これにより、依存度が偏っている部材や国を把握できます。
2. 自己評価(リスクアセスメント)
続いて、自社が直面するリスクを客観的に評価します。
- 依存度の高い原材料・地域・サプライヤーはどこか
- 供給が止まった場合、事業継続にどの程度影響するか
- 法規制や経済安全保障の観点からどんな脆弱性があるか
こうした観点で優先順位をつけることで、「まずどこから対策を打つべきか」が整理されます。
3. 強靭化の施策
評価を踏まえ、具体的な強靭化の取り組みに進みます。
- 調達の多元化:特定国や特定サプライヤーに依存せず、複数の調達ルートを確保
- 代替ルート・代替資材の検討:物流経路や原材料が遮断された場合に備えたバックアッププランを事前に準備
- 生産拠点の分散化:リショアリング・ニアショアリング※を含め、複数地域に生産機能を配置
- 在庫の適正水準設定:過剰在庫ではなく、リスクを吸収できる水準を設定
- デジタルモニタリングの導入:ESGデータ基盤やリスク可視化ツールを活用し、常時監視・アラートを実現
※リショアリング…一度海外へ移転した生産拠点や業務を、自国へ戻すこと
※ニアショアリング…生産拠点や業務を、自国から地理的・文化的に近い国へ移すこと
4. リスクモニタリングとシナリオ分析
単発の調査ではなく、継続的なリスクモニタリングを仕組み化することが重要です。地政学リスクの動向を定量的に把握し、複数のシナリオを設定して「収益や供給能力への影響」をシミュレーションすることで、迅速かつ柔軟な経営判断が可能になります。
5. 社内連携の強化
最後に、対応を「調達部門の努力」で終わらせないことが肝心です。
経営企画、法務、サステナ部門が横断的に連携し、戦略的に対応する体制を整えることで、初めて実効性のあるリスクマネジメントが実現します。
戦略的意思決定の補佐役「地政学リスクウォッチ」
地政学リスクは突発的に顕在化するため、「いまどの地域にどんなリスクが潜んでいるか」を定期的に最新情報として把握しておくことが重要です。とはいえ、個々の担当者が海外情勢や規制変更を逐一追いかけるのは現実的ではありません。そのために必要なのが、地政学リスクを定期的に把握する仕組みです。
地政学リスクを効率的に把握する方法とは?
- 直近の国際情勢を踏まえた地政学リスクを把握する
- 自社の対応状況を答えるだけで、スコアリングする
- 他社と比較することで、自社の立ち位置を認識する
このサイクルを繰り返すことは、地政学リスクに対する感度を高めていくことにつながります。決して他人事ではない地政学リスク。このスコアをもとに、経営陣と「自社はどのように備えていくのか」について、いち早く対話しておくことが重要です。
このようなリスクを可視化する仕組みは、企業にとって戦略的意思決定の補佐役にもなります。この仕組みを用いることで調達・企画・経営企画・サステナ部門が共通の前提に立った上で、迅速にリスク対応を議論できる基盤が整います。
当社は、地政学リスクへの自社対応状況に関する質問項目に回答することで、最新リスクの効率的な把握と、自社のリスク管理体制の強化を支援するサービス 「地政学リスクウォッチ」を提供しています。経済安全保障の観点から、自社のサプライチェーンや事業環境に潜む脆弱性を的確に見極める“リスクを見る目”を養い、リスクに強い企業へと進化していきませんか。サービス詳細はこちら
まとめ:地政学リスクへの取り組みはESG経営そのもの
地政学リスクへの対応は、単なる危機管理にとどまりません。調達・生産・販売といった事業活動の基盤を守ることは、そのまま「環境(E)」「社会(S)」「ガバナンス(G)」を強化する取り組みでもあります。
すなわち、 地政学リスクマネジメントは、ESG経営の要素であり、同時にサステナビリティ戦略の核心に位置づけられます。
企業がこうした取り組みを実効性のあるものとするために、ゼロボードでは以下のサービスをご用意しています。詳細は各サービスページをご覧ください。
地政学リスクウォッチ:最新地政学リスクの把握と管理体制構築を支援します。
Dataseed SAQ:バイヤーからサプライヤーに対するSAQ(Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート)の収集・管理を効率化するクラウドサービスです。
Zeroboard ESG:欧州CSRD、有価証券報告書・SSBJなどの国内外のサステナビリティ法定開示に耐えうるESGデータ収集・分析を行うことができます。
※1_出典:日本経済新聞_小麦価格、コメを逆転 ウクライナ侵攻で高騰https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB265TT0W2A420C2000000/(2022年5月7日)
※2_出展:JETRO_米中対立が対米サプライチェーンに与えた影響https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0904/299f5f4e8cb02b20.html(2023年10月16日)
※3_貿易ドットコム_イラン・イスラエル戦争が日本に与える影響:最新分析【2025年版】https://boueki.standage.co.jp/impact-of-the-iran-israel-war-on-japan/(2025年6月18日)