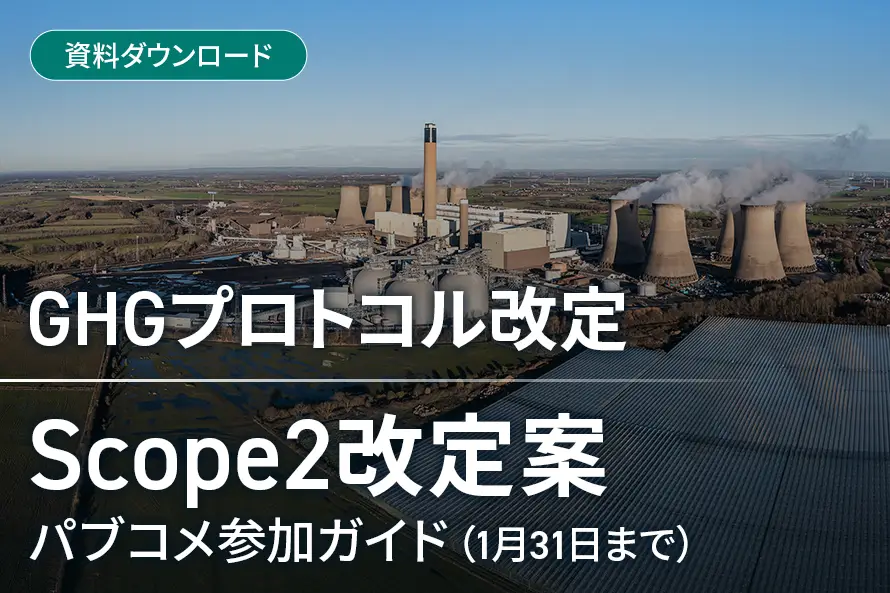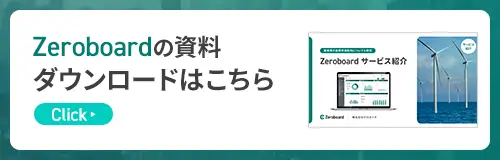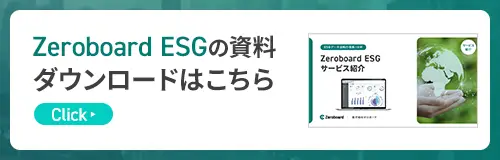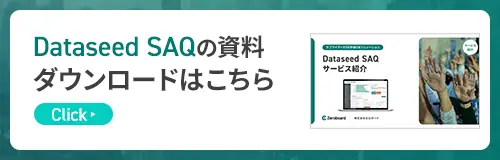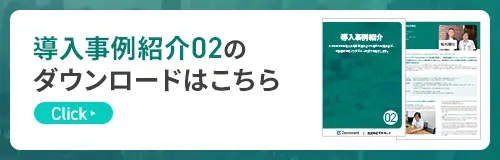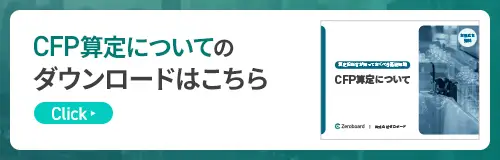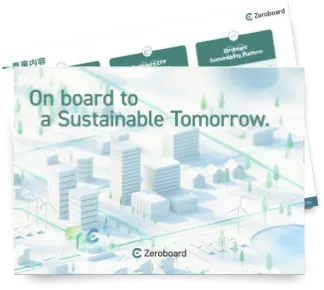排出原単位データベースとは?種類・ 活用方法・導入メリットを徹底解説

排出原単位データベースとは何か?
排出原単位(排出係数)を用いた温室効果ガス(GHG)排出量計算方法
排出原単位とは、特定の活動量(例:電力使用量、輸送距離、廃棄物量など)あたりの温室効果ガス排出量を示す指標です。*1)たとえば、電力1kWhの使用に伴うCO2排出量や、輸送1トンキロあたりの排出量などがそれに該当します。排出量の計算式は、以下の通りです。
排出量 (tCO₂e)= 活動量 × 排出原単位*1)
“tCO₂e”は“ton of CO₂ equivalent”(CO₂換算トン)を意味し、メタンや一酸化二窒素などのGHGをCO₂に換算するための単位です。*1)
この計算方法を用いることで、企業は自社の温室効果ガス排出量を具体的に把握でき、GHGプロトコルに則ったScope 1・Scope 2・Scope 3それぞれの排出量を正確に算定できます。
排出原単位(排出係数)データベースの定義
排出原単位データベースとは、CO2を含む温室効果ガス(GHG)排出量を計算するために必要な排出原単位(単位活動量あたりの排出量)を体系的にまとめたデータベースです。*2)このデータベースには、さまざまな活動やサービスごとのCO2排出原単位がまとめられており、サプライチェーン全体の排出量の算定や環境負荷の可視化に役立ちます。主に企業や自治体が自らの温室効果ガス排出量を定量的に評価し、削減計画の立案など脱炭素経営を進めるための基盤となります。*2)
排出原単位データベースの使い方
Scope 1、Scope 2、Scope 3別の算定と可視化の方法
各企業が排出量を把握する際には、Scope 1、Scope 2、Scope 3の3つのスコープに分類し、データを算定する必要があります。*2)その際、どの活動にどの原単位を当てはめるかを整理しておくと、算定がスムーズになります。GHGプロトコルに準拠したScope分類は以下の通りで、使用が推奨されるデータベースがが環境省から公表されています*2):
Scope 1(自社の直接排出)
対象:燃料使用や工場の工程による直接排出(輸送以外)
国内の参考データ
【SHK】温対法算定・報告・公表制度(環境省、経済産業省)*4)
【IDEAデータベース】(国立研究開発法人産業技術総合研究所)*5)
【J-LCA】(LCA日本フォーラム)※SHK対象外の活動のみ*6)
海外の参考データ
現地の制度やガイドライン
- 現地情報の収集が難しい場合は、IPCCガイドライン*7)を利用したり日本の係数を準用することが多い
Scope 2(購入した電気・熱使用による間接排出)
対象:自社が購入した電気や熱の使用
国内の参考データ
【SHK】温対法算定・報告・公表制度(環境省、経済産業省)*4)
海外の参考データ
現地の制度やガイドライン
難しい場合は、【IEA】*7)や【IGES】*8)の国別データ
Scope 3(サプライチェーンを含む間接排出)
Scope 3では、取引先やサプライチェーン全体を含む間接排出量が対象となり、データ収集が最も複雑ですし、カテゴリごとにデータの選び方が変わります。Scope 1・Scope 2以外の全ての間接排出で、調達・輸送・廃棄・資本財などバリューチェーン上のその他間接排出すべてを含みます。
国内の参考データ
【IDEAデータベース】(国立研究開発法人産業技術総合研究所)*4)
【SHK】温対法算定・報告・公表制度(環境省、経済産業省)*3)
【GLIO】(独立行政法人国立環境研究所)*9)
海外の参考データ
現地の制度やガイドライン
海外排出原単位データベース
排出原単位が満たすべき要件
使用する「排出原単位」がどのようなデータかによって、計算の正確さ(精度)や算定範囲(カバー率)が変わってきます。排出原単位が満たすべき代表的な要件は以下の通りです。*2)
排出原単位の要件*2)
- 信頼性:データの出典や情報源が明確で、追跡できること。
- 代表性:利用するデータが、時間・地域・技術の観点で算定対象を適切に代表していること。
- 時間的適合性:データが古すぎず、算定時点に近いものを使うこと。毎年更新されるデータは直近のものを使用し、数年ごとに更新される場合もできるだけ新しいデータを選ぶ。
- 地理的適合性:算定対象の活動が行われている地域のデータを優先すること。もし該当データがなければ、他地域のデータで代替してもよい。
- 技術的適合性:対象とする活動に使われている最新または現行の技術を反映していること。
上流工程を含むデータベース活用の重要性
企業の脱炭素経営を進めるうえで欠かせないのが、「サプライチェーン全体の排出量を正確に把握すること」です。とくに、製品やサービスの環境負荷を評価する際には、原材料の採取から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまでを含むライフサイクル全体のデータ(上流データ)をどこまでカバーできるかが算定精度を大きく左右します。
環境省が公表している排出原単位データベース(Ver.3.5など)は、主に企業活動におけるエネルギー使用や廃棄物処理など、企業の直接的な排出量(Scope 1、2中心)を対象にした国内標準の算定基盤です。
一方で、こうした公的データの多くは、原材料の採掘・製造・輸送といった上流工程に関する排出量(Scope 3に相当する関節排出)までは十分にカバーされていません。
そのため、製品やサービスのライフサイクル全体(原材料調達~廃棄まで)を考慮した排出量の把握には、LCA(ライフサイクルアセスメント)に基づく国際的な排出原単位データベースの活用が欠かせません。
代表的なものに、日本の「AIST-IDEAデータベース」や、スイスの「ecoinvent」があります。これらは、上流・下流工程を含めた包括的な環境負荷データを網羅的に提供しており、素材や部品の製造段階を含めたサプライチェーン全体の精緻な排出量算定を可能にします。
主な排出原単位データベース種類と選び方
国内の代表的な排出原単位データベース*2)種類と選び方
国内の代表的な排出原単位データベース比較表(環境省排出原単位データベースVer3.5より)*2)
データベース | 提供元 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |
SHK(温対法算定・報告・公表制度)*4) | 環境省・経済産業省 | 産業連関表をもとに平均排出原単位を整備 | ◎社会全体を網羅し幅広い業種に対応○Scope 3初期算定に便利 〇電力・燃料・廃棄物処理などの係数を網羅。 | ●部門分類が粗く、個別精度は低い | 全体像の把握、簡易算定 |
GLIO(Global Link Input-Output)*9) | 国立環境研究所地球環境センター(Center for Global Environmental Research, NIES) | 国際的に拡張した産業連関表 | ◎海外サプライチェーンも含め算定可能 | ○国内詳細分析には不向き | 輸入品や国際取引を含む算定 |
IDEA v3(Inventory Database for Environmental Analysis)*5) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST) | 原材料の採取から廃棄までのプロセスを精密に積み上げて算出された国内有数のDB | ◎製品・工程に即した高精度な算定が可能◎製品単位のLCA(ライフサイクルアセスメント)に基づく詳細な排出原単位データベース | ●整備に労力大○有料ライセンス | 製品LCA、精緻な算定。製造業や調達部門での排出量可視化。 |
海外の代表的な排出原単位データベース*2)種類と選び方
海外の代表的な排出原単位データベース比較表*2)
データベース | 提供元 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |
ecoinvent*11)(スイス) | 非営利団体(ecoinvent Association) | 世界で最も広く利用されるLCAのDB。各国・各分野の詳細プロセスデータを収録。 | ◎エネルギー・資材・化学品など幅広い分野をカバー◎ISO 14040/44準拠で国際的信頼性が高い | ○有料ライセンス○日本固有のデータは少ない | グローバルLCA、海外取引対応。国際的なサプライチェーンを持つ企業や、欧州規則 |
ELCD(European Reference Life Cycle Database)*12) | 欧州委員会(JRC) | 欧州域内の共通基盤データとして整備され、EU政策対応や規制準拠に広く用いられるLCAデータ | ◎公的機関が整備し信頼性高い◎欧州規制対応に有効 | ○対象は主に欧州域内○更新頻度は限定的 | 欧州での環境対応、研究 |
US LCI(United States Life Cycle Inventory Database)*13) | 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL) | 米国特有の産業・エネルギー構造に基づくLCAデータ | ◎無償公開で利用しやすい◎米国市場向け分析に有効 | ○データ範囲がまだ限定的○整備状況が分野によりばらつき | 米国での事業展開、学術研究 |
GREET(Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation)*14) | アルゴンヌ国立研究所(米国) | 特に輸送・燃料分野に特化したLCAモデル | ◎自動車・燃料サプライチェーンの分析に強い◎政策や規制対応に活用される | ○適用分野が限定的(主に輸送関連) | 輸送部門の排出量算定、燃料分析 |
排出原単位データベースを使ったCO2排出量の可視化
事業者は算定範囲や求める精度に応じて柔軟にデータを選択することで、より信頼性の高いGHG排出量の算定が可能になります。また、サプライチェーン全体の可視化や、国際的なESG報告(例:TCFD、CDP)開示への対応も一層スムーズになります。*3)
具体的なデータ収集および活用の流れ
排出原単位データベースを活用したCO2排出量の算定は、以下のステップで行います。*2)
1.自社の活動量の把握
電力量、燃料使用量、輸送トンキロ、金額ベースなど、対象範囲に応じた活動量データを収集します。
2.排出原単位の選定
Ver.3.5に掲載された産業連関表ベースまたは積み上げ法(IDEA v3)ベースの排出原単位から、対象とする活動に最も近いカテゴリの値を選定します。
3.排出量の算定
算定式「排出量(tCO₂e)=活動量×排出原単位」を用いて、各活動の排出量を計算します。
4.可視化と活用
算出結果を部門別・工程別に可視化し、排出の多い部分の特定と削減対策の優先順位付けに役立てます。
サプライチェーン全体での排出量把握の重要性
サプライチェーン全体でのCO2排出量を把握することは、企業が効果的な脱炭素戦略を実行する上で欠かせない要素です。自社の直接的な排出量だけでなく、取引先やサプライチェーンの上流・下流の排出量も含めた視点を持つことで、全体的な排出量を正確に評価することが必要です。*3)
温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)*16)と排出原単位データベースの連携
温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)は、世界で広く採用されている温室効果ガス排出量の算定・報告のための枠組みです。排出原単位データベースはこのプロトコルと連携する形で活用され、企業が排出量を分類・算定する際に役立ちます。*2)
特にScope 3における包括的な排出量把握には、サプライチェーン全体の排出データが必要です。環境省による「排出原単位データベースVer3.5」を参考に整備された最新のデータベースを、活動ごとに適切に選択して利用することで、データの精度を向上させながら、プロトコルに準拠した排出量算定を可能にします。*2)
※ZeroboardはAIST-IDEAデータベースを標準搭載し、上流データを含めた精緻な算定を実現:当社サービスでは、LCAやScope 3による環境負荷の計算と可視化、CFP算定を支える日本世界最大規模のLCAインベントリデータベースであるAIST-IDEAデータベースのGHG排出量算定に特化した項目を厳選搭載しています。Scope 1~3までの包括的なGHG排出量の可視化を高精度かつ効率的に実現します。国内外のLCA・ESG要件にも対応できるため、サプライチェーン全体の脱炭素経営を支援する基盤として、多くの企業に選ばれています。


参照元
*1)環境省 日本国温室効果ガスインベントリ報告書2024年https://www.env.go.jp/content/000226851.pdf
*2)環境省:排出原単位データベースVer.3.5(2025年3月公開)https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
*3)環境省:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出源単位について(Ver.3.5)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/unit_outline_V3-5.pdf*4)環境省・経済産業省「温対法 算定・報告・公表制度」SHK
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html*5)産業技術総合研究所(AIST)IDEA公式サービス解説
https://www.aist-solutions.co.jp/service/aist_idea/aist_idea.html*6)国立環境研究所・環境省監修「IPCC温室効果ガスインベントリガイドライン」https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/
*7)国際エネルギー機関(IEA)
https://www.iea.org/*8)地球環境戦略研究機関(IGES)「国別温室効果ガス排出量データ」
https://www.iges.or.jp/jp*9)国立環境研究所地球環境センターGLIO(Global Link Input-Output)データベースhttps://www.cger.nies.go.jp/publications/report/d031/index.html
*10)国立環境研究所 「3EID(産業連関表による環境負荷原単位データベース)」
https://www.nies.go.jp/3eid/index.html*11)ecoinvent Association「ecoinvent Database」
https://ecoinvent.org*12)欧州委員会(European Commission,Joint Research Centre,JRC)「European Reference Life Cycle Database(ELCD)」
https://eplca.jrc.ec.europa.eu/ELCD3/*13)米国国立再生可能エネルギー研究所(National Renewable Energy Laboratory, NREL)「United States Life Cycle Inventory Database(US LCI)」 https://www.lcacommons.gov/lca-collaboration/NREL
*14)米国アルゴンヌ国立研究所(Argonne Naional Laboratory, USA)「GREET(Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation)」公式サイトhttps://greet.es.anl.gov/
*15)環境省「Q&A サプライチェーン排出量算定におけるよくある質問と回答集」
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/QandA_202303.pdf*16)World Resources Institute(世界資源研究所 WRI), World Business Council for Sustainable Development(世界経済人会議 WBCSD)「GHG Protocol」
https://ghgprotocol.org/corporate-standard