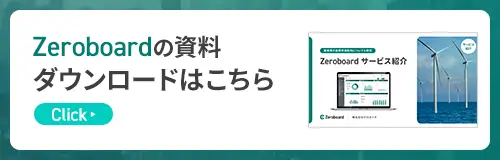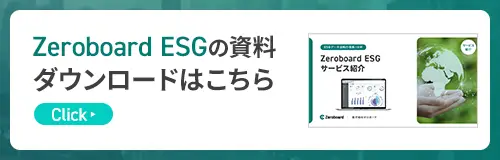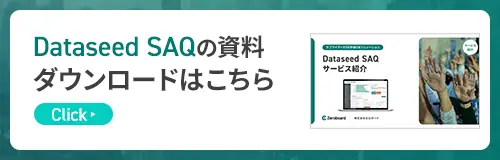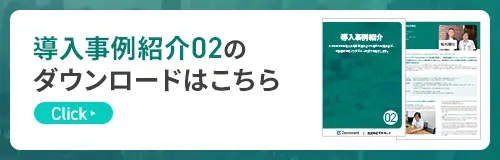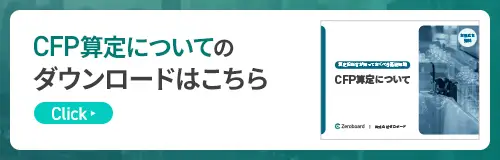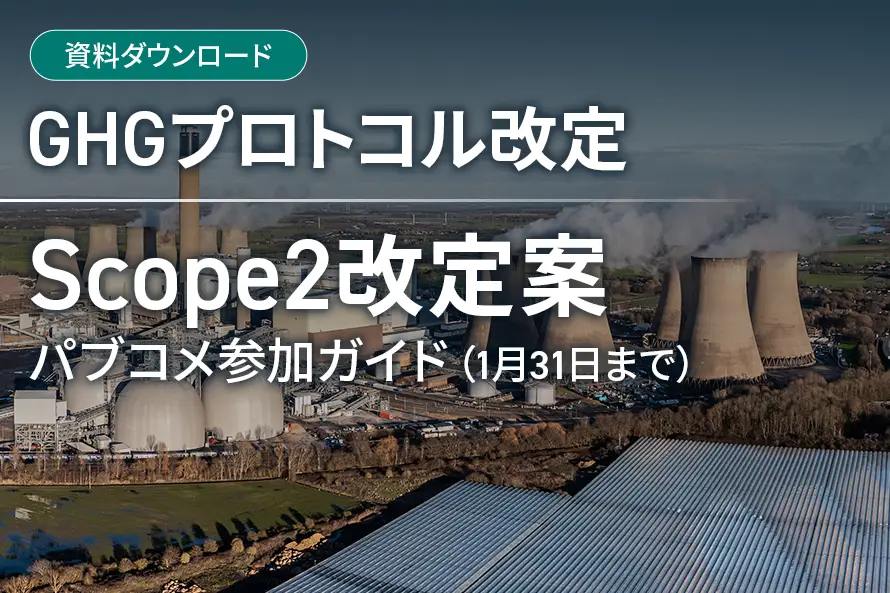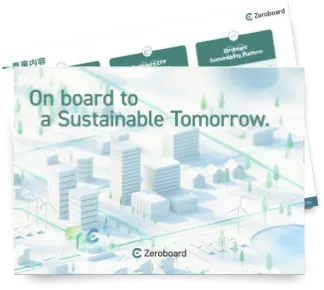SBT認定(Science Based Targets)とは?取得方法やメリット、認定の仕組みを紹介

社会的な企業のサステナビリティ活動に関する関心の高まりから、企業の温室効果ガス削減活動についても、それが本当に意味があるものであることを説明することが求められるようになってきています。
そうした背景から近年注目されているのが、SBT(Science Based Targets)と呼ばれる科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減目標です。2025年9月現在、日本のSBTi参加企業は1,900社超に上り、国別参加数で世界最多を誇るSBT先進国となっています。*1)
SBT(Science Based Targets)が企業にもたらす5つのメリット
2015年にフランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)では 、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べ2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑えることを目指す「パリ協定」が採択されました。その後、2021年のIPCC第六次評価報告書*3) において1.5℃目標に関するシナリオが取りまとめられ*4)*5) 、また、関連する知見も蓄積されており、現在では1.5℃に抑えることを前提とした削減目標や、気候変動に関する戦略を検討する事業者が多くなっています。
SBTは「パリ協定」を達成するために、科学的根拠に基づいた数値をもって企業が設定する温室効果ガスの削減目標です。WWF、CDPなど4つの組織が設立した国際イニシアティブ(プロジェクト機関)のSBTi(Science Based Targets Initiative)が、ガイドラインの整備や認定を行っています。*1)
SBTの認定取得には一定の準備やコストが必要ですが、そうした負担に値するだけのメリットがあるのも事実です。
【SBT認定取得のメリット】*1)
【SBT認定取得メリット①】企業価値の向上
SBT認定の取得は脱炭素化への取り組みを対外的に示す指標となり、企業評価の向上に役立つ。またSBT認定はCDPの加点対象となっておりCDPスコア向上につながることから、ESG投資を志向する機関投資家、金融機関からの投資の呼び込み効果が期待される。
【SBT認定取得メリット②】競争力の向上
顧客がScope 3の削減目標を設定していた場合、サプライヤーへも温室効果ガスの削減を求める可能性がある。そのような場合SBTを取得し、自社の削減目標を明確にしておくことは、そうした要望への迅速な対応を可能にし他社との差別化を生むことから、競争力の向上に繋がる。
【SBT認定取得メリット③】サプライチェーンのレジリエンス向上
自社がSBTにおいてScope 3の削減目標を設定した場合、その達成仮定においてサプライチェーンへのコミュニケーションを実施することが多い。そういったコミュニケーションはサプライヤーのサステナビリティに関する対応を促す効果が副次的にあるため、サプライチェーン全体で環境対策に取り組むことで、調達リスクや規制強化へのリスクなど、サプライチェーン上に潜む様々なリスクを低減できる。
【SBT認定取得メリット④】イノベーション
SBT目標の達成に向け再エネ導入や省エネ、技術開発などに取り組むことで、コスト削減・業務効率化といったイノベーション効果が期待できる。
SBT認定の条件とは?:Scope別の要件を解説
SBTの認定基準について、主だった要点を以下にまとめます。*1)
・定められた統合アプローチに従った企業全体のScope 1およびScope 2のGHGが対象。多くの場合、子会社や、一部のJV(ジョイントベンチャー)を含む。
・基準年は2015年以降でデータが存在する最新年を推奨。目標年は申請時から最短5年、最長10年以内。
・Scope 1およびScope 2の目標設定は必須。Scope 3排出量が総合計の40%以上となる場合はScope 3の目標設定も必須。
・Scope 1、Scope 2は総量削減で年4.2%以上を削減目安とし、1.5℃以内の気温上昇に抑えるよう目標を設定。
・Scope 3は総量削減で年2.5%の削減を目安に、気温上昇を2℃以内に抑える目標を設定。
SBT認定の申請プロセスとステップごとの流れ
SBT認定の取得は以下の手順で進めます。*1)
1.アカウントの作成
検証ポータルでアカウントを登録。企業規模等(中小企業か否かなど)を確認。
↓
2.コミットメント(任意)
2年以内に目標設定を行う旨のコミットメントレターを事務局に提出。
↓
3.GHG排出量の算定/目標の策定
Scope 1~3のGHG排出量を算定し、SBT基準に整合する削減目標を設定する。
↓
4.目標の提出/申請費用の支払い
検証ポータルにデータを入力することで申請。併せて検証に関する契約を実施し、請求書に対する支払いを実施する。
↓
5.審査
申請データと公開情報(ウェブサイトなど)の整合性、目標の妥当性などを事務局が検証。指摘を受けた場合には不適合箇所を修正して再提出する。
↓
6.認定/公表
認定後、6か月以内にSBTiウェブサイトにて公表される。
↓
7.定期的な報告/目標の確認
認定後は年に1回、GHG排出量と対策の進捗状況の報告・開示を行う。また定期的に目標の妥当性を確認する。
※条件等の情報は、2025年9月時点の内容であり、変更になる場合があります。
企業規模によるSBT認定の違い*1)
SBT認定では、企業規模によって認定要件や目標設定、費用に違いがあります。日本の中小企業の一般的な定義とは異なるため、自社がどの分類に当てはまるかを正しく把握することが認定取得の第一歩です。
中小企業版SBTの条件
・Scope 1、Scope 2排出量:合計1万トン未満
・非再生可能エネルギー資産を保有していない
・海上輸送船や火力発電所など、大量排出源は中小企業扱い外
・非金融セクターであること
・金融機関は独自基準が適用されます
・大企業の子会社ではないこと
・子会社の場合は親会社を通じて認定取得
上記の必須条件に加え、以下の3条件のうち2つ以上を満たす必要があります。
・従業員数:250名未満
・年間売上高:5,000万ユーロ未満(約80億円)
・総資産:2,500万ユーロ未満(約40億円)
企業規模が目標設定に与える影響
中小企業
・Scope 1、Scope 2の目標設定が必須
・Scope 3は算定のみで削減目標設定は任意
大企業
・Scope 1~3すべての目標設定が必須
・削減率の目安:Scope 1、2は年4.2%以上、Scope 3は年2.5%以上
企業規模による申請費用の違い
企業規模や申請条件により申請費用は異なります。セクター別の目標等を含まない、Near-Term目標のみの設定の場合は以下の通りとなります。
中小企業
・初回申請:1,250ドル
大企業
・初回申請:11,000ドル
・目標再設定:5,500ドル
※条件・費用等の情報は、2025年9月時点の内容です。
SBT認定取得でよくある実務課題とその解決策
SBT認定取得に向けては、企業グループ間を横断してのデータ収集、Scope 3の算定、英語でのやり取りなど、SBT認定の実務担当者が直面する問題は少なくありません。加えて、申請プロセスの複雑化や、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするネットゼロ基準の導入など、SBTを取り巻く状況が厳格化しています。
こうした状況の中で認定を目指すにあたっては、企業が抱える課題を精査し、優先順位をつけて対応していくことが不可欠です。当社では、実際にこうした課題に直面した企業様のSBT認定取得を支援してきました。
ゼロボードの伴走支援でSBT認定を取得された企業の具体的な事例を公開しています。取り組みの流れや成果をぜひご覧ください。→https://www.zeroboard.jp/case/infroneer
経験豊かなエキスパートが支えるZeroboard(温室効果ガス算定・可視化ツール)の導入支援とコンサルティングサービス(SBT認定支援サービス)
SBT認定取得には、GHG排出量の算定や削減目標の設定、申請プロセスなど専門知識が不可欠です。ゼロボードでは、環境データの一元管理から申請支援、実務上の課題解決まで、経験豊富なエキスパートが企業ごとに伴走しサポート。SBT認定取得まで安心して進められる体制を提供します。


<出典元>
*1)環境省、グリーン・バリューチェーンプラットフォーム https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/decarbonization_05.html
*2)WWFジャパン、Science Based Targetsイニシアティブ(SBTi)とはhttps://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/409.html
*3)IPCC, 2021. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/*4)環境省, 2021. 「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)」
https://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/*5)国立環境研究所, 2022. 「IPCC第6次評価報告書(AR6)の概要」
https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/adapt/a-0504.html