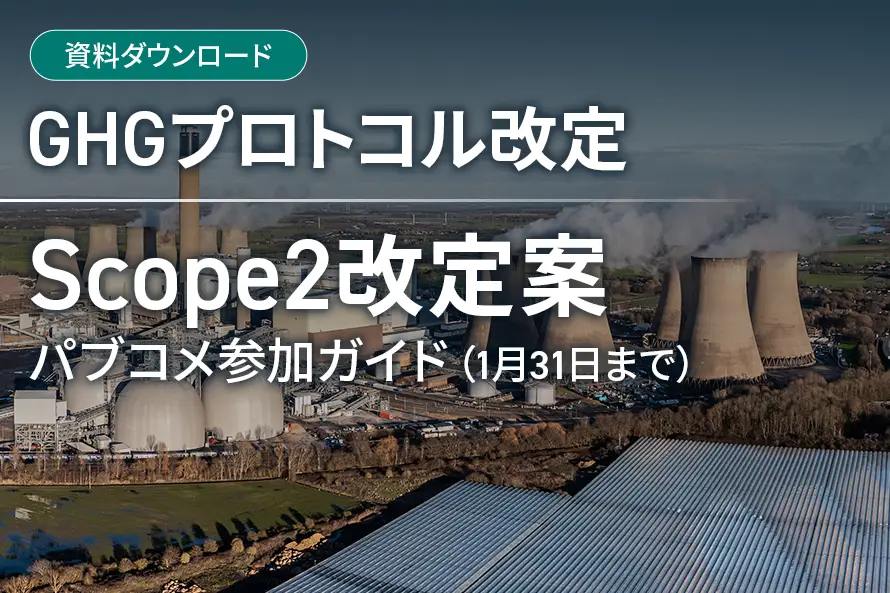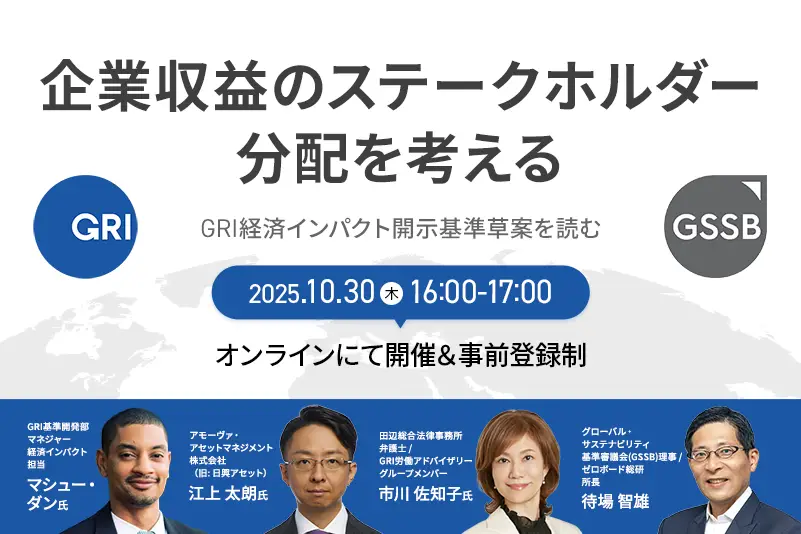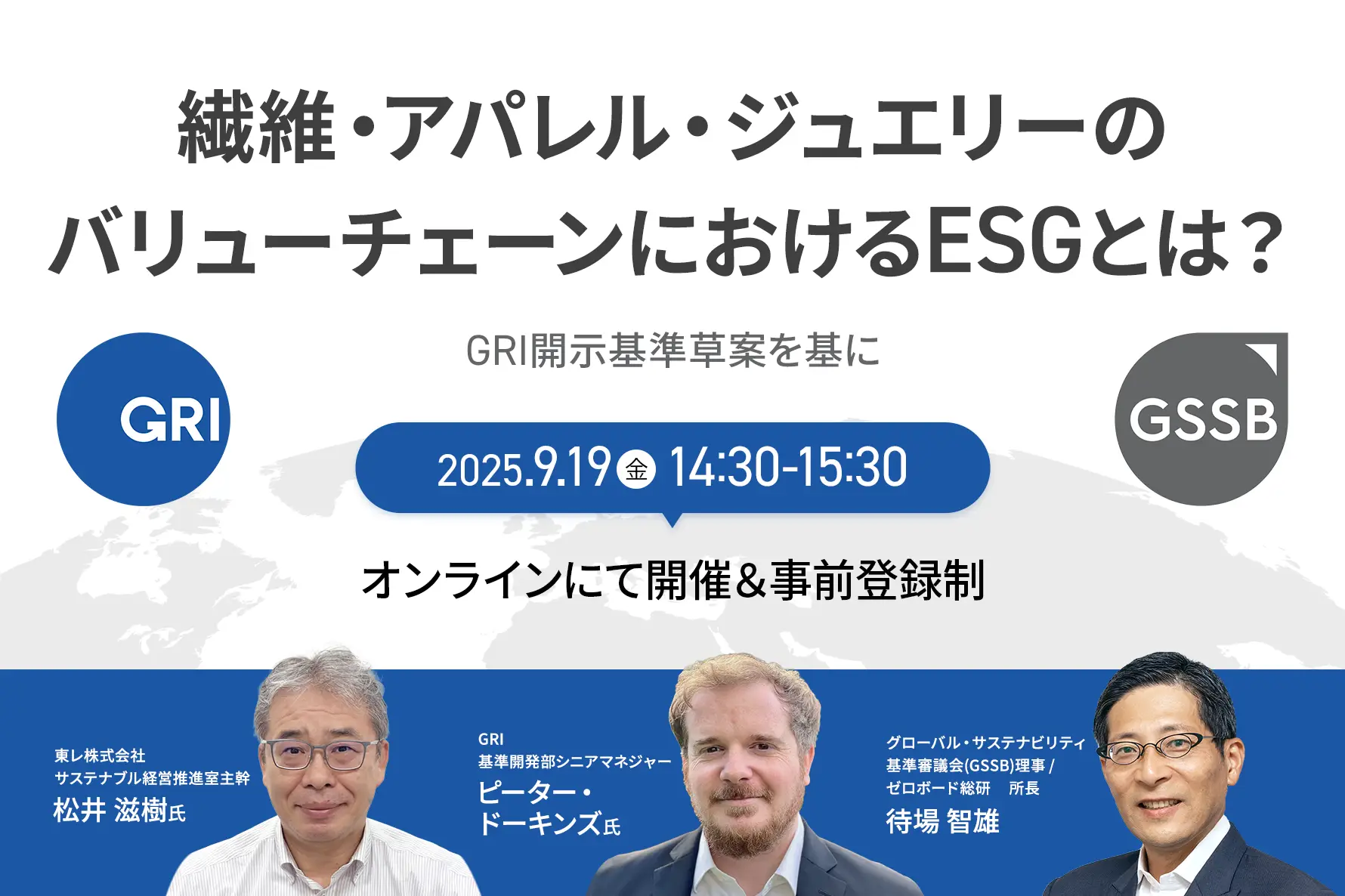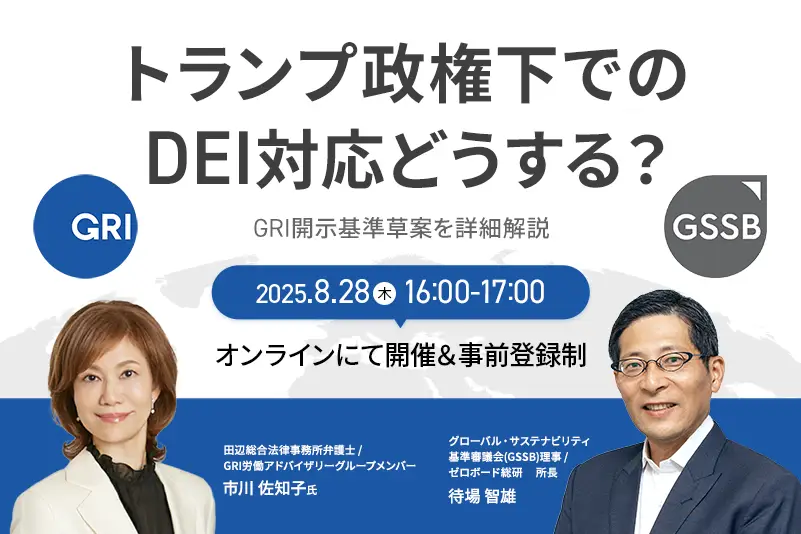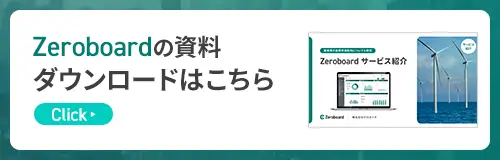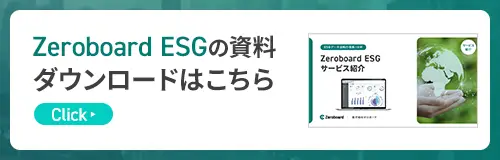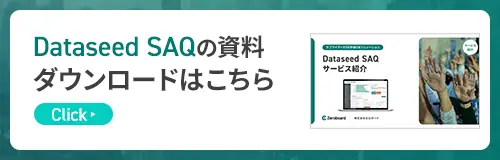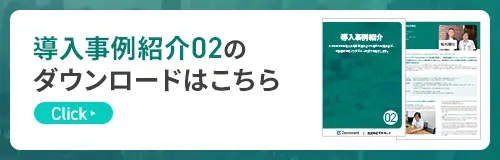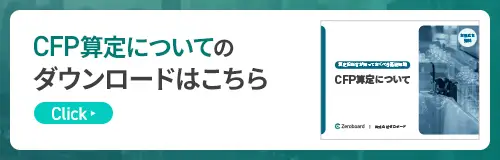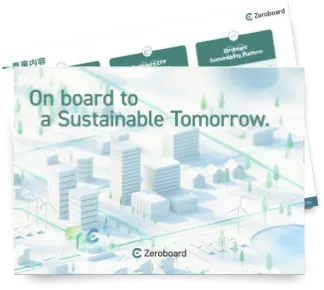国際的なサステナビリティ開示基準:GRIスタンダードの基礎と最新動向

GRIスタンダードとは?
GRI設立の背景と目的
GRI(Global Reporting Initiative)は1997年に米国ボストンで設立された国際的な非営利団体です。その前身はNPOのCERESとTelus Instituteであり、国連環境計画(UNEP)も設立に関与しています。当初の目的は、企業が環境に対する責任ある行動原則を遵守していることを確保するための説明責任メカニズムを構築することでした。その後、その活動範囲は社会、経済、ガバナンスの課題にも拡大し、企業が持続可能な発展に貢献するための包括的な報告フレームワークを提供しています。※1
非財務情報開示の国際動向との関係(ISSB/ESRS/TCFDなど)
GRIスタンダードは、企業の非財務情報開示に関する国際的な動向の中で重要な役割を担っています。近年、投資家が企業のESG(環境・社会・ガバナンス)課題への取り組みを投資判断に組み入れる「責任投資」が拡大しており、財務情報以外の企業情報に対するニーズが高まっています。このような背景から、気候変動対策や環境課題への対応に関する情報開示の必要性が高まり、GRIの他にもさまざまな開示基準が提唱されるようになりました。
主な国際的な開示基準とGRIスタンダードとの関係性は以下の通りです。
ISSB(国際サステナビリティ基準審議会):IFRS財団が設立した基準策定機関で、投資家向けのサステナビリティ開示基準(IFRS S1/S2)を開発しています。GRIとISSBはMOUを締結し、GRIスタンダードとISSBの基準が相互に補完し合う関係性を構築しています。ISSBが「財務関連性(Single Materiality)」に焦点を当てる一方、GRIは「インパクト(社会・環境への影響、Double Materiality)」の視点を重視しています。
ESRS(欧州サステナビリティ報告基準):EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づき、欧州企業に義務付けられる開示基準です。GRIはESRSの開発に技術支援を行い、GRIスタンダードとESRSは高い整合性を持つことが確認されています。ESRSに準拠して報告する企業は、GRIスタンダードを参照して報告しているとみなされる場合が多いです。
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース):気候変動関連の財務リスクと機会に関する情報開示を推奨するフレームワークです。2023年にその使命を終えて解散し、現在はISSBの基準に統合されています。ただし各国の制度や企業実務においては依然として「TCFDに沿った開示」という表現が広く使われており、GRIスタンダードは、TCFDの推奨事項に沿った気候関連情報の開示をサポートする役割も果たします。
GRIスタンダードは、これらの多様なグローバル開示フレームワークを統合的に活用したい企業にとって重要な基準となっており、国際的な情報開示の「土台」としての役割を担っています。
基準・枠組み | 策定主体 | 主な対象 | 重要性の視点 | 特徴 | GRIとの関係性 |
ISSB (IFRS S1/S2) | IFRS財団 | 投資家 | 財務的重要性(Single Materiality) | 投資判断に必要な情報を重視 | GRIとMOU締結、補完関係 |
ESRS | EU(EFRAG) | EU域内企業(CSRD対象) | ダブルマテリアリティ | 義務的開示基準、GRIと整合性あり | GRI参照が認められる |
GRIスタンダード | GRI(独立組織) | すべてのステークホルダー | 社会・環境インパクト(Double Materiality) | 任意基準だが世界的に普及 | 他基準の“土台”となる |
TCFD | FSB(現在はISSBに統合) | 投資家・金融市場 | 財務的重要性(気候に特化) | 気候関連の財務リスクと機会に焦点 | GRIが気候情報開示を補完 |
主要なサステナビリティ開示基準(GRI・ISSB・ESRS・TCFD)の比較表
GRIスタンダードの構成
GRIスタンダードは、報告組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを報告し、持続可能な発展への貢献を説明するためのフレームワークを提供します。2016年にGRIガイドラインに代わって公表され、2021年10月には共通スタンダードの改訂版※2が公表されました。 GRIスタンダードはモジュール形式になっており、定期的に更新されることで、最新のサステナビリティ課題や規制要件に対応しています。
GRIスタンダードは、以下の3つの構成要素から成り立っています。
ユニバーサル基準
すべての報告組織に適用される基本的な基準です。これらは「GRI 1:基礎」「GRI 2:一般開示事項」「GRI 3:マテリアルな項目」の3つから構成されています。
GRI 1:基礎(2021)
GRIスタンダードの利用方法や、報告原則の適用に関する指針が示されています。GRI 2:一般開示事項(2021)
報告組織の背景情報に関する開示事項を定めています。組織の詳細、活動、ガバナンス構造、戦略、方針、実務慣行、ステークホルダー・エンゲージメントなど、多岐にわたる項目が含まれます。GRI 3:マテリアルな項目(2021)
組織にとってマテリアル(重要)な項目を特定し、そのマネジメント手法を報告する際の指針を提供します。マテリアリティ評価のプロセスや、人権デュー・ディリジェンスを含む責任ある企業行動のための方針声明に関する開示事項が追加されています。
トピック基準
組織が自己にとってマテリアルな経済、環境、社会の各インパクトについて報告するために選択する基準です。これらの基準は「200番台(経済)」「300番台(環境)」「400番台(社会)」のシリーズで構成されています。
経済(200番台)
経済パフォーマンス、税金、調達慣行、腐敗防止などに関する開示事項が含まれます。環境(300番台)
エネルギー、水と廃水、生物多様性、大気への排出、廃棄物など、環境に関する広範なテーマをカバーします。社会(400番台)
雇用、労働安全衛生、研修と教育、多様性と機会均等、人権、地域コミュニティなど、社会的な側面に関する開示事項が含まれます。
セクター基準(概要紹介/詳細は別記事リンク予定)
特定のセクター(産業)に特有のインパクトに関する報告を可能にする基準です。セクター基準は、企業がそのセクターで重要と思われるトピックを特定し、マテリアリティ評価を支援するために開発されています。
例:
GRI 11:石油・ガス(2021)
GRI 12:石炭(2022)
GRI 13:農業・養殖業・漁業(2022)
セクター基準は順次拡張されており、今後も新たなセクターが追加される予定です。これにより、各産業の特性に応じた、より具体的で網羅的なサステナビリティ報告が可能になります。セクター基準の具体的な内容については、別記事で詳細を解説します。
最新の改訂・動向(2025年時点)
GRIスタンダードは、サステナビリティ報告の進化に合わせて継続的に改訂・拡張されています。2025年時点での主な改訂・動向は以下の通りです。(2025年10月現在)
気候変動・エネルギー基準(素案)
GRIは、2025年に向けて新たな気候変動関連基準「GRI 102 気候変動 2025」および「GRI 103 エネルギー 2025」をローンチする予定です。これらの新基準は、脱炭素経営の実態と影響を包括的に可視化する枠組みを提供します。これらの素案は2025年7月初旬に公開され、9月末までパブリックコメントが募集されました。現在は寄せられた意見を踏まえた最終化プロセスが進められており、正式発行後は既存基準に置き換える予定です。
GRI 102 気候変動 2025
- GHGプロトコルに準拠したスコープ1〜3排出量の算定を要求します。
- 科学的根拠に基づいた「移行計画」や「公正な移行」に関する開示を求めます。
- 世界の気候目標に沿った温室効果ガス(GHG)排出削減を支援するツールとして機能します。
GRI 103 エネルギー 2025
- 組織の脱炭素・省エネへの取り組み、化石燃料および再生可能エネルギーの使用状況に関する開示を求めます。
- 責任あるエネルギー利用についての情報開示を促します。
これらの基準は、GRIと整合性の高いESRSやIFRS・SSBJ両サステナビリティ開示基準との併用にも対応しており、多様なグローバル開示フレームワークを統合的に活用したい企業にとって重要です。
DEI(多様性・公平性・包摂性)対応基準
GRIでは現在、労働関連のトピック基準群を対象に段階的な改訂を進めており、その第3フェーズとして「労働者の権利と保護」に関する2つの新スタンダード草案を公開しています。
2025年5月に公表されたのは、次の2つの草案です。
- GRI無差別スタンダード(Non-discrimination Standard:公開草案/英語)
- GRI多様性とインクルージョン(Diversity and Inclusion Standard:公開草案/英語)
これらは、従来の「GRI 405:多様性と機会均等(2016)」を刷新し、差別の禁止、公平な待遇、包摂的な職場環境づくりに関する開示項目を強化する内容となっています。両基準草案に対するパブリックコメントは2025年9月15日まで募集されました。
GSSB(Global Sustainability Standards Board)の承認を経て、最終版が発行される予定です。
改訂の背景には、企業におけるDEI(Diversity, Equity, and Inclusion)の重要性が一層高まっていることがあります。企業の多様性指標(性別・年齢・民族・障がい・社会的少数派属性など)に加え、昇進や報酬、差別防止措置、包摂的文化の醸成といった実務レベルでの取り組み開示が求められています。
セクター基準の拡張(繊維・アパレル、金融)
セクター基準は、各産業の特性に合わせた開示を可能にするために順次拡張されています。特に、繊維・アパレル産業や金融セクターは、環境・社会への影響が大きいことから、それぞれのセクターに特化した基準の重要性が高まっています。
金融セクター:金融セクターは、投融資活動を通じて環境・社会・経済に広範な影響を与えることから、最も注目度の高い分野の一つです。投融資先の環境・社会への影響(ファイナンスド・エミッション)、人権デュー・ディリジェンス、責任投資への取り組みなど、金融機関固有の開示が求められます。
2024年には、以下の3つのセクター基準が相次いで発行されました。繊維・アパレル産業:繊維・アパレル産業は、原材料調達から製造・販売まで幅広い工程で環境・人権リスクを抱える分野として、国際的にも注目されています。2025年7月には、繊維・アパレル産業向けセクター基準(Textiles and Apparel Sector Standard)の草案が公開され、9月29日までパブリックコメントが募集されました。サプライチェーン全体を通じた環境負荷(化学物質、水資源、廃棄物など)や労働環境、公正賃金、人権デュー・ディリジェンスといった課題の開示を強化する内容となっています。
日本企業にとっての意義
投資家・規制当局からの期待
GRIスタンダードは、世界中の多くの企業で採用されており、日本企業においてもその利用が広がっています。KPMGの調査によると、2020年には日経225企業の73%がGRIスタンダードを利用しています。この背景には、ESG投資の拡大に伴い、国内外の投資家が企業のサステナビリティ情報開示に強く期待していることがあります。また、国内においても金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令」改正など、非財務情報開示を求める規制の動きが進んでおり、日本企業はこれらの期待と規制に適切に対応する必要があります。GRIスタンダードに準拠した報告は、投資家や規制当局に対して、企業のサステナビリティへの取り組みの透明性と信頼性を示す重要な手段となります。
統合報告・サステナレポートとの関係
多くの日本企業は、統合報告書やサステナビリティレポートを通じて非財務情報を開示しています。GRIスタンダードは、これらの報告書の作成において活用される主要なフレームワークの一つです。
統合報告書:GRIスタンダードは、統合報告書における非財務情報の網羅的な開示をサポートします。特に、マテリアリティ評価を通じて特定された重要課題に関する情報は、企業の価値創造ストーリーと結びつける上で有効です。
サステナビリティレポート:GRIスタンダードは、サステナビリティレポートの根幹となる情報開示の基準を提供します。共通スタンダード(GRI 1-3)やトピック基準(200-400番台)に沿って、経済、環境、社会の各側面のインパクトを詳細に報告することで、ステークホルダーに対して透明性の高い情報を提供できます。
日本企業では、GRIスタンダードを「参照」して報告書を作成しているケースが多いですが、今後は「準拠」して報告する企業が増えることが予想されます。
実務対応で押さえるべきポイント
GRIスタンダードを実務で活用する上で、日本企業が押さえるべきポイントは以下の通りです。
マテリアリティ評価の深化:GRIスタンダードでは、組織が経済、環境、人権を含む人々に与える最も著しいインパクトをマテリアルな項目として特定することを求めています。単なる関心事項の羅列ではなく、バリューチェーン全体での潜在的・顕在的な影響を特定し、優先順位付けを行う「ダブル・マテリアリティ」の視点を取り入れることが重要です。
最新版GRIスタンダードへの対応:2023年1月以降に発表されるGRI対照表は、新しい共通スタンダード(GRI 1, 2, 3)に対応する必要があります。特に、GRI 3で示されるマテリアリティ特定方法の改訂点を理解し、自社の報告プロセスに組み込むことが求められます。
セクター基準の活用:自社の属するセクターの基準が公表された場合、それを参考にすることで、業界特有の重要課題に対する網羅的かつ質の高い情報開示が可能になります。未公開の場合でも、SASBなどの他の業界別開示基準を参照して、産業特性を考慮したマテリアリティ特定に努めるべきです。
他の開示フレームワークとの連携:ISSBやESRS、TCFDなど、複数の開示フレームワークが並存する現状では、それぞれの特徴を理解し、GRIスタンダードと組み合わせて戦略的に活用することが重要です。例えば、投資家向けの財務関連情報にはISSBやTCFDを、より広範なステークホルダー向けのインパクト情報にはGRIを活用するなど、目的に応じた使い分けや統合的な開示戦略が求められます。
DEIに関する情報開示の強化:多様性、公平性、包摂性への社会的な要請が高まる中、GRI 405に沿ったDEIに関する具体的なデータ開示(例:女性管理職比率、男女間賃金格差など)を強化し、その取り組みを明確に伝えることが期待されます。
よくある質問(FAQ)
GRIスタンダードは義務か?
GRIスタンダードは、国際的なサステナビリティ報告のための自主的なガイドラインであり、法的な報告義務を課すものではありません。しかし、世界中の多くの企業が参照しており、特に上場企業やグローバル企業にとっては、投資家やその他のステークホルダーからの期待に応える上で事実上の「国際標準」として広く認識されています。また、欧州のESRSのように、GRIスタンダードと高い整合性を持つ報告基準が法制化される動きもあり、間接的に報告が求められる状況も増えています。
ESRSやIFRSとの違いは?
ESRS、IFRS(ISSBの基準)、GRIスタンダードは、いずれもサステナビリティ情報開示に関するフレームワークですが、その目的や焦点に違いがあります。
GRIスタンダード:企業が社会や環境に与える「インパクト」に焦点を当てた、マルチステークホルダー向けの包括的な開示基準です。財務的影響だけでなく、企業活動が外部に与える影響(ダブル・マテリアリティ)を重視します。
ESRS:EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づく、EU域内の大企業等に義務付けられる開示基準です。GRIスタンダードと同様に「ダブル・マテリアリティ」の視点を取り入れており、GRIとの整合性が高いです。
IFRS(ISSBの基準):投資家向けのサステナビリティ開示基準であり、サステナビリティ関連のリスクと機会が企業の財務に与える影響(シングル・マテリアリティ)に焦点を当てています。TCFDの提言をベースにしており、財務情報との関連性を重視します。
これらの基準は、それぞれ異なる視点を持つものの、相互運用性を高めるための協力が進められており、企業は複数のフレームワークを組み合わせて活用することが一般的になっています。
パブリックコメントは企業に関係ある?
GRIスタンダードやその他の国際的な開示基準の改訂・策定プロセスでは、パブリックコメント(公開草案に対する意見募集)が実施されます。これは、基準の最終化にあたり、企業、投資家、NGOなど、幅広いステークホルダーの意見を反映させるための重要なプロセスです。
企業がパブリックコメントに関与することは、以下の点で関係があります。
将来の開示要件への理解:公開草案を通じて、将来的に求められる開示内容や方向性を早期に把握できます。
企業活動への影響評価:自社の事業活動や開示体制に、新たな基準がどのような影響を与えるかを評価できます。
基準策定への影響:自社の意見を表明することで、基準の内容に影響を与え、より実務に即した、あるいは自社に有利な基準となる可能性もあります。
特に、最新の改訂動向に関心のある企業にとっては、パブリックコメントの機会を活用し、積極的に意見を提出することが有益です。
まとめ:GRIスタンダードを理解し実務へ活かす
GRIスタンダードは、企業のサステナビリティ情報を網羅的かつ透明性高く開示するための国際的な基準です。その歴史、包括的な構成、そして継続的な改訂は、企業が社会や環境に与えるインパクトを理解し、責任ある経営を実践する上で不可欠なツールとなっています。
特に、以下の点を理解し、実務に活かすことが重要です。
GRIスタンダードは、単なる報告義務ではなく、企業の長期的な価値創造と社会的信頼構築のための戦略的なツールであること。
ユニバーサル基準、トピック基準、セクター基準の三層構造を理解し、自社のマテリアリティに応じた適切な項目を選択・開示すること。
最新の改訂動向、特に気候変動・エネルギー基準やDEI対応、セクター基準の拡張に注目し、常に最新の情報にアップデートすること。
ISSBやESRSなど、他の国際的な開示フレームワークとの関係性を踏まえ、統合的な開示戦略を構築すること。
GRIスタンダードを深く理解し、その原則と要件を実務に落とし込むことで、日本企業は国内外のステークホルダーからの期待に応え、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。
出典:
※1:GRI「ビジョン・ミッション・歴史」
https://www.globalreporting.org/about-gri/vision-mission-and-history/
※2:GRI「GRIスタンダード改定に関して」
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/universal-standards/