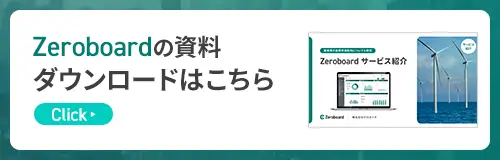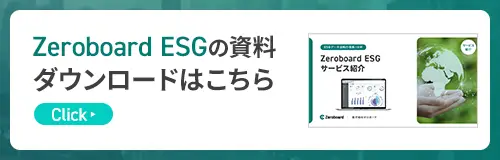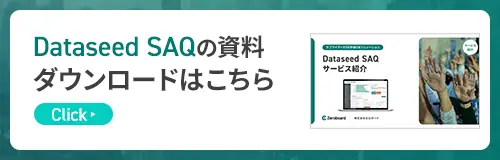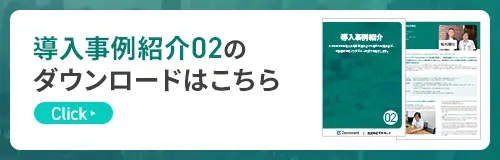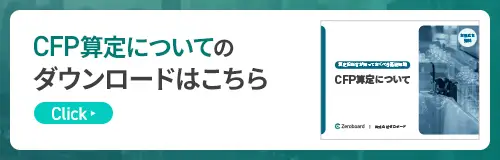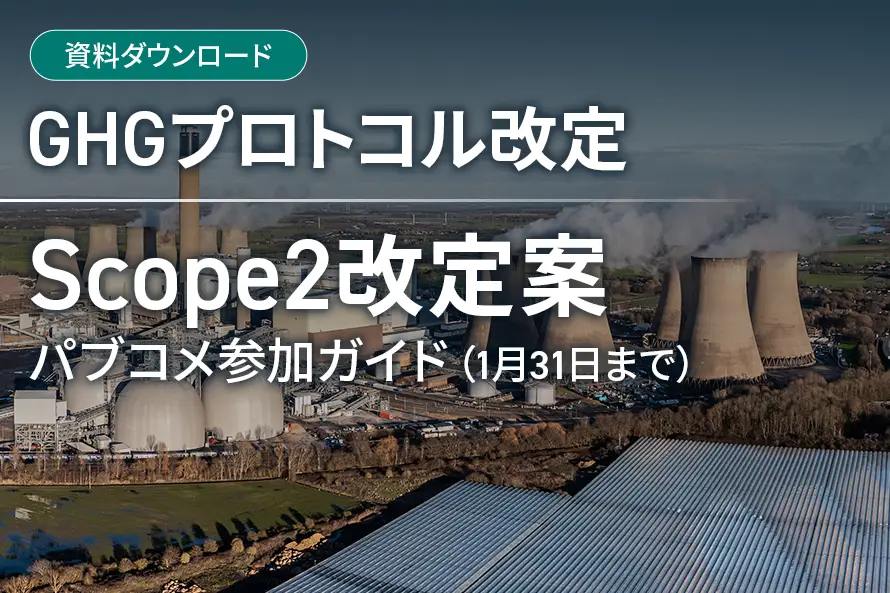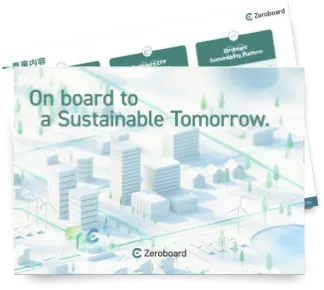加速する気候変動と向き合う─奄美大島に残された生物多様性の記憶

ゼロボード総研所長 待場 智雄
一足早くに夏休みを取り、初めて奄美に出かけてきた。昨秋、神童と言われながら画壇では芽が出ず、千葉から奄美に移住、死後になって評価された田中一村の東京都美術館での回顧展*1)を観て、普通日本画では見られない南国の鮮やかな色彩に魅了されたことがきっかけである。
東端の奄美空港周辺のリゾート感あふれるビーチやサトウキビ畑を抜け、まず大島紬の工房を訪れる。地元に生えるシャリンバイの木をチップにして大釜で煮出したものを染料とし、これで褐色になった生糸を泥田に持って行って、泥にくぐらせる。泥に含まれる鉄分と染料のタンニンが化学反応を起こし少しずつ黒くなっていくのだが、これを80~100回も繰り返すのだという。私もベテランの職人さんに全く聞き取れない奄美言葉を教えてもらいながら、のれん生地を泥染めする体験をさせてもらったが、世界でも唯一というこの天然染色法を今も手作業で続けているというのに驚いた。さらに大島紬は糸自体を各々のパターンに染めてから織るということで、その細かく根気のいる作業を見ると、値段が張ることも納得できた。一村もこの糸を染める仕事をして生活費と画材費を稼ぎ、絵を描いていたのだという。
 泥染めを体験する筆者と染め上がったのれん島の中央部に位置する金作原(きんさくばる)原生林に向かった。ここは2021年7月に世界自然遺産に登録されるのを見越して、認定ガイドがないと入れないようにし、ツアー業者の車台数などを制限して、自然を守れる範囲で観察を楽しむエコツーリズムを実践している*2)。猛毒を持つハブが多く生息するため島人たちはあまり山に入らなかったので、ハブが人間から森を守ってきたといえる。辺りを見回すと動植物も内地とは大きく異なり、すっかり熱帯雨林のジャングルかジュラシックパークな風情だ。突如とんでもない豪雨に見舞われ、映えスポットという巨大なシダ植物ヒカゲヘゴの写真を撮るのもままならなかったが、木々が濡れると緑色が映え、一村が描きトトロも傘に使ったクワズイモ(サトイモそっくりだが食べられない)の美しさがよく感じられた。
泥染めを体験する筆者と染め上がったのれん島の中央部に位置する金作原(きんさくばる)原生林に向かった。ここは2021年7月に世界自然遺産に登録されるのを見越して、認定ガイドがないと入れないようにし、ツアー業者の車台数などを制限して、自然を守れる範囲で観察を楽しむエコツーリズムを実践している*2)。猛毒を持つハブが多く生息するため島人たちはあまり山に入らなかったので、ハブが人間から森を守ってきたといえる。辺りを見回すと動植物も内地とは大きく異なり、すっかり熱帯雨林のジャングルかジュラシックパークな風情だ。突如とんでもない豪雨に見舞われ、映えスポットという巨大なシダ植物ヒカゲヘゴの写真を撮るのもままならなかったが、木々が濡れると緑色が映え、一村が描きトトロも傘に使ったクワズイモ(サトイモそっくりだが食べられない)の美しさがよく感じられた。
南西部の住用湾の河口には、西表島に続いて国内2番目に広いマングローブ林が広がっていて、カヤックで見て回ることができる。ツアーに参加せず道具だけ借りたので、ゆったり岸辺に寄ってマングローブに宿る小さなカニを見たり、水の中の魚を覗いたりしていると、いつの間にか潮の満ち引き次第で川にでも海でもなる広大な水辺の中にいた。
 金作原原生林のヒカゲヘゴとクワズイモ
金作原原生林のヒカゲヘゴとクワズイモ
さらに奄美大島からフェリーで20分渡り、東西に広がる人口1,000人ほどの加計呂麻(かけろま)島にも足を伸ばし、スキューバダイビングを楽しんだ。大島海峡(瀬戸内とも言う)は波が穏やかなわりに海底地形が複雑になっていて、大小の様々な魚やサンゴやイソギンチャクが彩る海の中から上を見上げ、岩の間を通して海面に差し込む日の光を見るのは何とも美しい。今回見られなかったが、この地固有のアマミホシゾラフグが繁殖時に海底に幾何学模様のサークルを作るのが有名で、冬にはザトウクジラと一緒に泳げるのだという。
島北西端の実久(さねく)集落のビーチは遠浅の白い砂浜が長く続き、水の透明度から「実久ブルー」と呼ばれるそうだが、シュノーケルを着けて潜ってみると、サンゴがことごとく死んでいて魚の姿もほとんど見られなかった。昨夏は高温に加え台風の接近が少なく、平均海水温が前年より1~2℃高く30℃を超え、実地調査によると奄美大島周辺のサンゴの約6割が白化してしまったのだそうだ*3)。1998年以来26年ぶりの大規模白化とのことで、コンクリート色になったサンゴの隅でかろうじて色の付いた箇所に小魚がしがみついているのを見て、サンゴが生きていることがいかに海の生態系に大切かを実感した*4)。
映画「男はつらいよ」の最終作が撮影されたという島南東端の徳浜は、南太平洋のようなラグーンが目の前に広がっているのだが、実久よりは魚が見られたとはいえ、同じくサンゴの白化は深刻だった。海の家を営む女性の話を聞くと、今年はウミガメが浜に来ても卵を産まずに帰っていくのだという。生物多様性に恵まれた地域で自然と直に面している人ほど、気候変動を毎日肌身で感じ、そしてこれから負の影響を被るのだろう。
人間による直接的に生態系をかく乱する心ない行為も後を絶たない。7月、国立公園内でネットにバナナを入れて木にかけるなど違法な昆虫採集用のわなが15個見つかった*5)。5月には、販売目的で国の天然記念物オカヤドカリ約5,200匹を捕獲したとして中国籍の男3人が検挙された*6)。奄美大島と徳之島にのみ生息する特別天然記念物アマミノクロウサギの2024年の交通事故死は両島合わせて163件で、高止まりが続いているという*7)*8)。
 徳浜ビーチと浜で見かけたオカヤドカリ
徳浜ビーチと浜で見かけたオカヤドカリ
奄美でも他の地方と同様に多くの古い木造民家が放置され、そのまま朽ち果てていっている。奄美大島出身の建築家・山下保博氏が空き家や空き店舗を宿泊施設に改造し、観光客と地元住民の交流を図る「伝泊」という社会的事業を展開しており、加計呂麻島にも2軒そうした宿がある*9)。町おこしの事例として全国から注目されており、大島側ではあるが今回その1軒に泊まることができた。
大島海峡を望む両岸は太平洋戦争で重要な拠点となり、加計呂麻島の薩川湾には大和や武蔵など連合艦隊の戦艦が停泊したという*10)。海軍は木製モーターボートの先端に爆弾を積んで体当たり攻撃をする特攻艇「震洋」を同島に配置し、小説家・島尾敏雄が第十八震洋特攻隊隊長を務めていた。1945年8月13日に出撃命令を受けたが、発進の号令を受けぬまま終戦を迎えた。島で出会ったミホと結婚したが、自身の浮気で妻が精神をきたし極限状態に至った夫婦間の葛藤を描いた私小説『死の棘』は、後に小栗康平監督によって映画化され、カンヌ映画祭で審査員グランプリを取っている*11)。また「奄美妻」といえば、西郷隆盛が奄美に遠流となった折に2番目の妻となった愛加那が知られる*12)。
滞在最後の夜、食堂で島唄の生演奏を聞きながら店員さんに「横浜から来た」と言うと、「実は僕も横浜にいたんですよ。消防士してました」との返事。聞くと、横浜市消防局の隊員に地元出身者は少なく、全国各地から集まって寮生活をしているという*13)。この間の参院選では「日本人ファースト」との訴えへの支持が高かったが、経済格差の下に外国人だけでなく地方の人たちも都市の低賃金で危険な仕事を担っている事実(さらに時代を遡れば、集団就職、そして余剰人口を国外に移民として送り出していたこと)、そしてそれへの感謝の念を忘れてはならないと改めて思った。
先の徳浜は巨大なロウニンアジが釣れることで知られ、釣り人が早朝からグループで来て、午後には帰ってしまうという。海の家の女性(缶コーヒー頼んだだけだったのに、話を聞くうちにフルーツやら近所の人が釣ったアジの刺身をごちそうになりました)は、「釣り人も海水浴客も海辺を荒らして、島を全然見ずに帰って行く。大勢でなく少しの人がここの時間をゆっくり楽しんでくれるといいんだけど…」となげく。都会に住む者の勝手な思いだろうが、大規模リゾート開発や「ジャングリア」もまだない奄美が、生態系と島人のペースを乱さない程度で今後も持続できることを心から願った。
*1) 東京都美術館「田中一村展 奄美の光・魂の絵画」、2024年9月19日~12月1日 https://isson2024.exhn.jp/
*2) 鹿児島県奄美市「金作原で利用ルールを導入しています」、2025年6月1日 www.city.amami.lg.jp/wnhs/kinsakubaru.html
*3) 朝日新聞「奄美のサンゴ6割死滅、26年ぶりの大規模白化 高い海水温影響か」、2024年12月14日 https://digital.asahi.com/articles/ASSDF1S1WSDFDIFI00TM.html
*4) WWFジャパンの2025年4~7月の大島郡大和村での調査では、一部にはサンゴ生存・回復の兆しも確認され、水深10m以下では白化の影響は見られなかったとし、今後継続的にサンゴの耐性や回復状況を調査するという。(奄美新聞社「サンゴ礁保全プロジェクト始動」、2025年7月24日 https://amamishimbun.co.jp/2025/07/24/57257/)
*5) 朝日新聞「国立公園内に違法な昆虫採集わな、警告も無視 環境省が奄美署に通報」、2025年7月17日 https://digital.asahi.com/articles/AST7J2V7ZT7JTLTB005M.html
*6) 読売新聞「チェックアウト後預かった中国人の荷物から異音、中には国の天然記念物」、2025年5月30日 www.yomiuri.co.jp/national/20250530-OYT1T50053
*7) 朝日新聞「アマミノクロウサギ、事故死163件 昨年」、2025年5月19日 https://digital.asahi.com/articles/AST5L3W7KT5LTLTB002M.html
*8) FNNプライムオンライン「絶滅危惧種のウサギや“日本一美しいカエル”の姿も…世界自然遺産登録から4年の奄美大島の今」、Yahoo! Japanニュース、2025年7月19日 https://news.yahoo.co.jp/articles/a8a008456b06c9b784fd44b4984ba934427c2af0
*9) 伝泊ホームページ https://den-paku.com
*10) 離島旅行のすすめ「史上最大の戦艦 大和や武蔵も停泊していた薩川湾 加計呂麻島」、2024年4月1日 https://remoteisland.info/satsukawa-kakeroma
*11)デイリー新潮「自らの不倫が引き金となった“一家の無間地獄” 作家・島尾敏雄が『死の棘』で描いた夫婦の修羅はどのような結末を迎えたか」、Yahoo! Japanニュース、2025年5月3日 https://news.yahoo.co.jp/articles/0bd436d23ed0776643fdf3fdcc0fe5a44a74601d
*12) BUSHOO! JAPAN「西郷2番目の妻・愛加那~菊次郎を産んだ奄美大島の島妻はどんな女性だった?」、2024年8月26日 https://bushoojapan.com/jphistory/baku/2024/08/26/109104
*13) 横浜市消防局の最近の採用試験合格者の約3分の2が県外となっている。(横浜市消防局人事募集リーフレット https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/saiyo/saiyou.files/0032_20230426.pdf)