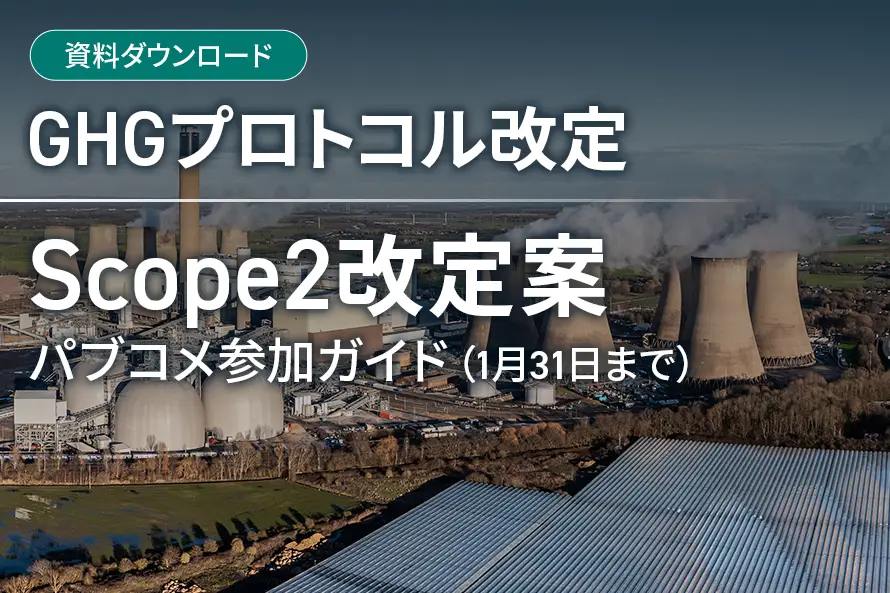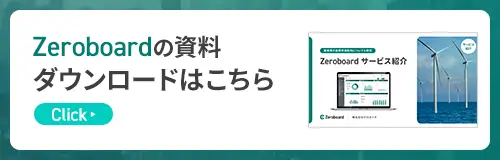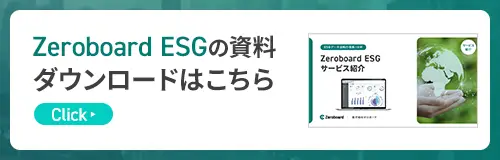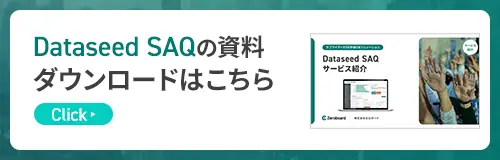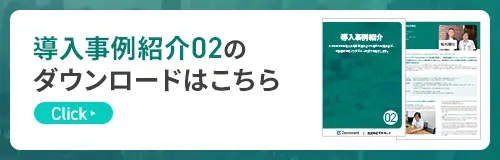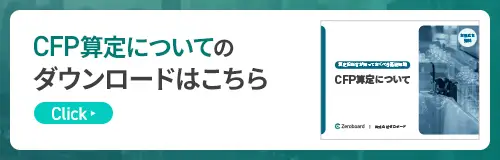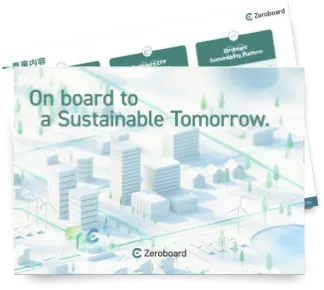CBAMとは何か? EUの炭素国境調整メカニズムをわかりやすく解説

気候変動対策が加速する中、EU(欧州連合)が導入を進める「CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism/炭素国境調整メカニズム)」は、グローバルビジネスのルールを大きく変えつつあります。鉄鋼やアルミニウム、セメント、電機、水素など、特に温室効果ガス(GHG)排出量の多い製品を対象に、EUは輸入時にも“炭素コスト”を課す仕組みを整備しています。
この制度は、EU域内の炭素削減努力と国際的な公平性を両立させることを目的としており、日本を含む貿易相手国の企業にも、GHG排出量の可視化や正確な報告体制の構築が求められます。製品設計やサプライチェーン戦略への影響も無視できません。
本記事では、CBAMの目的や仕組み、導入スケジュールから、日本企業がとるべき基本的な対応策まで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
CBAMとは何か?
CBAMの概要と目的
CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism/炭素国境調整メカニズム)とは、EU(欧州連合)が策定した新しい環境規制の枠組みで、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力などの高炭素集約型の輸入製品 に対し、炭素排出コストを課す仕組みです。この制度の主な目的は、EU内での炭素削減努力を維持しつつ、EUの排出量取引制度(EU ETS)との公平性を確保し、カーボンリーケージ(Carbon Leakage)を防ぐこと にあります。※1
カーボンリーケージ とは、高い環境基準を持つ国で規制が厳しくなることで、企業が生産拠点を規制の緩い国へ移し、結果的にグローバルな温室効果ガス(GHG)の排出削減が進まなくなる現象を指します。
このメカニズムにより、EU内の企業と海外からの輸入業者が同様の炭素コストを負担することで、公平な競争環境を確保し、グローバルなサステナビリティ推進に寄与することを目指しています。
導入の背景とEUの狙い
CBAMの導入背景には、EUの気候変動対策の強化と経済的公平性の確保という2つの狙いがあります。EUは、1990年比でGHG排出量を2030年までに55%削減する目標を掲げ、その実現のために2021年に包括的な法改正パッケージ「Fit for 55」を発表しました。※2 この中核に位置するのがCBAMで、特にセメント、鉄鋼、アルミ、肥料、水素、電力といった高炭素排出製品を対象としています。加えて、CBAMはEU ETS(EU排出量取引制度)がカバーできない輸入品の炭素排出コストを調整し、EU内外の競争条件を公平にする役割を果たします。
EUはこれを通じて、国際的な環境基準を引き上げるとともに、他国にも同様の炭素価格制度の導入を促し、地球規模での脱炭素化を加速させることを目指しています。
CBAMとカーボンプライシングの関連性
CBAMの仕組みは、EU ETS(排出量取引制度)との相互補完関係に基づいています。
EU ETSでは、EU域内での排出権取引に基づき、炭素排出にコストが課されますが、輸入製品はその対象外となるため、不均衡が生じる可能性があります。
この問題を解消するため、CBAMは海外からの対象製品にEU ETSと同等の炭素価格を適用する仕組みを導入しています。これは、カーボンプライシングの一環として位置付けられ、、グローバルな炭素削減を促進する制度として期待されています。
その結果、EUだけでなく貿易相手国にとっても、炭素排出削減への圧力となると同時に、自国でのカーボンプライシング導入を検討する契機となる可能性があります。
CBAMの仕組みを解説
炭素排出コストがどのように計算されるか
CBAMでは、輸入製品の炭素排出コストが計算され、輸入者はそのコストに相当するCBAM証書を購入することで負担します。この計算には、EUの排出量取引制度(EU ETS)に基づく炭素価格が適用されます。具体的には、報告されたデータや標準排出係数に基づいて算出し、その量に炭素価格を掛け合わせることでコストが算出されます。この計算は、EU域内の生産者と同等の炭素コスト負担を求めることで、公平な競争環境を維持することを目的としています。
例えば、鉄鋼やセメントのようにエネルギー消費の大きい製品は、それに伴う排出量が具体的に計算され、その結果が製品の炭素コストに反映されます。この仕組みは、企業が排出コストの低い国へ生産拠点を移すことによる温室効果ガス排出増加(カーボンリーケージ)を防ぐ役割も果たします。
対象となる製品と輸入者の義務
CBAMの対象製品には、セメント、鉄鋼、アルミ、肥料、電力、水素などが含まれます。これらの製品は、製造過程で大量のGHGを排出するため、規制の対象として選定されています。CBAMの適用により、輸入者はCBAM証書を購入する義務を負います。※3
Annexes to the CBAM Implementing Regulation for the transitional phaseを基にZeroboardにて作成
輸入者には、「認可CBAM申告者」としての登録が求められ、対象製品の輸入に際して、詳細な報告義務を果たす必要があります。※4
具体的には、製品の製造過程における製品の製造過程で排出されたGHG(温室効果ガス)の詳細な報告が必要です。この報告は、2023年~2025年の移行期間中は四半期ごとの報告が義務付けられており、正式導入後は年間報告が基本となります。そのため、輸入者は製造元との連携を強化し、排出量データの取得と管理体制の整備を進める必要があります。※5
2024年2月のオムニバス法案による制度変更
2024年2月、欧州委員会はCBAM制度に関する運用見直しを含むオムニバス法案を提出し、輸入者の義務や制度の運用面でいくつかの重要な変更が加えられました。これにより、報告やデータ取得に関する負担を軽減しつつ、制度の明確化と整合性の確保が図られています。
主な変更点は以下の通りです。
- CBAM証書初回購入時期を2027年2月以降に延期(但し2026年輸入分から適用)
- 輸入量が少ない事業者に適用される「ディ・ミニミス閾値」の導入
- 軽微な加工・組立を施した製品(仕上げ工程)をCBAM対象から除外
- EU産原料に由来する排出量は報告対象外とするルールの明確化(ダブルカウント防止)
- デフォルト値の使用要件が柔軟化され、地域平均値の活用が可能に
- CBAM証書の購入・償却・管理方法に関する要件の明確化(2026年以降の本格適用に備えて)
これらの変更により、日本を含むEU域外の輸出企業にとって、排出量報告やデータ管理に関する実務のハードルは一定程度緩和される見込みです。一方で、制度への対応に向けた準備は引き続き不可欠であり、移行期間中に各社が必要な体制整備を進めることが求められます。
CBAMの導入スケジュール
移行期間(2023年10月〜2025年12月)
CBAMは2023年10月1日より移行期間が開始され、2025年末まで実施される予定です。企業は制度に順応するための時間を与えられるだけでなく、システム全体の運用に関してEU側が必要な改善を行う期間としても活用されます。
この期間中、CBAM対象製品の輸入者には、排出量の報告義務が課されますが、課金(CBAM証書の購入)は不要です。
移行期間は、含有排出量のデータ収集・報告の準備期間としても位置付けられています。
本格適用期間(2026年1月〜)
CBAMの本格適用は2026年1月より開始され、ここからは実際に炭素排出コストが課されるようになります。※6 企業は、毎年5月末までに、前年度の輸入量に応じたCBAM証書を購入・償却する必要があります。
適切な対応を怠った場合、最大で1tCO₂あたり100ユーロの罰則が科される可能性があり、データの正確性と管理体制の整備が極めて重要となります。
CBAMの導入がもたらす影響
EU域内の産業への影響
CBAMの導入は、EU域内の産業にさまざまな影響をもたらします。まず、EU内の製造業者においては、域外からの安価な製品と競争する上で公平性が確保されるとされています。特に、鉄鋼やアルミなどのエネルギー集約型産業においては、安価な輸入品が自社の市場を脅かす懸念が軽減されるため、CBAMを歓迎する声もあります。
一方で、EU内部においても、生産効率の低い企業や炭素排出量の高い事業者が、競争力を失うリスクがあります。高い環境基準を求められる中で、これらの企業は迅速な対応が求められるため、コストの増加や制度適応の負担が発生します。特にCBAM規制に基づき、GHG排出量に基づく炭素コストの適用が進むことで、企業の経営戦略にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
対象国の反応と影響
CBAMの導入は、対象国においても、経済的・政策的な広範な影響を及ぼします。EUがグローバルサプライチェーンにおいて炭素価格を設定するメカニズムを初めて取り入れたことで、輸出国は生産時の炭素排出量を透明性高く報告する必要があります。※7 この報告義務に対応するため、多くの国が制度整備や技術的な対応を求められています。
一部の国からは、「国境調整」という仕組みが新たな関税障壁として機能するのではないかという懸念が挙がっています。特に開発途上国を中心に、こうした制度が国際貿易や経済成長に悪影響を与えるとの指摘が多くなされています。一方、環境意識が進んでいる一部の先進国では、CBAMを自国の規制と連携させつつ輸出を促進させる取り組みが進んでいます。
日本企業への具体的影響
影響を受ける業界
日本企業の中でも、特に鉄鋼、アルミニウム、化学品、電力関連業界がCBAMの影響を大きく受ける可能性があります。
2021年時点で日本の対EU輸出総額の約1.9%がCBAM対象製品に該当しており、今後の適用範囲の拡大によりさらなる影響が予想されます。
日本からEU向けに輸出される鉄鋼やアルミなど、対象製品の生産者は、GHG排出量の透明性向上や削減努力を迫られることになります。特に報告義務の導入により、輸出企業は既存プロセスを見直し、自社のサプライチェーン全体での炭素排出量を正確に把握する必要が生じます。
さらに、CBAMに基づく炭素コストが商品価格に影響を及ぼすことで、価格競争力を維持するためには、製品設計や生産工程の見直しが必要です。また、日本企業は炭素削減技術への投資を加速させる必要があり、環境規制に対応することで、サステナビリティを高める戦略が求められています。特に高炭素集約型セクターにおいては、EU市場での競争力を維持するために、長期的な視野での炭素排出の削減計画が重要となるでしょう。
具体的な対応策
日本企業がCBAMに対応するためには、以下の取り組みが必要です。※8
1.炭素排出量の可視化と報告体制の構築
- 自社およびサプライチェーン全体のGHG排出量を正確に把握し、CBAMレジストリへの適切な報告を行う。
- 各製品の排出量を算定し、EU規制に適合した形で提出できる体制を整備する。
2.低炭素技術への投資
- CBAM証書の購入コストを削減するために、GHG排出量の少ない製造プロセスを導入する。
- 低炭素・ゼロカーボンの技術開発や再生可能エネルギーの活用を強化する。
3.EU市場での競争力維持
- CBAM対応によるコスト増を価格転嫁するか、競争力を維持するための戦略を検討する。
- EU域内の取引先との連携を強化し、サプライチェーン全体での低炭素化を推進する。
CBAMに関する課題と今後の対応
WTOルールとの整合性
CBAMの導入において最も注目される課題の一つが、WTO(世界貿易機関)のルールとの整合性です。
CBAMはEUが国内の環境政策を維持しつつ、競争条件を公平に保つことを目的としていますが、炭素価格を調整する形で輸入製品に関税のような仕組みを適用するため、一部の対象国や企業からは「非関税障壁」や「保護主義的規制」と受け取られる可能性があります。
WTOを基盤とした多国間貿易秩序では、国境調整税や関税に関連する取り決めが厳密に行われているため、この制度が環境保護目的として正当性を有するかが議論の焦点となりそうです。
これに対して、EUはCBAMが気候危機への主要な対応策となることを強調し、国際社会に正当性を訴え続けています。
グローバルサプライチェーンの影響
対象製品である鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力を含む産業において、途上国や先進国問わず輸入者が対応を求められることで、生産コストの上昇や供給体制の見直しが必要になる場合があります。
特に、多数の国をまたいで製品を製造するグローバル企業では、サプライチェーン全体の炭素排出量評価や、報告義務への対応が大きな課題となります。
また、CBAMが厳格に運用されることで、炭素排出量が多い国からの輸出競争力が低下する可能性があるため、全体の市場構造にも変化をもたらすことが予想されます。
今後の国際連携と制度拡大の可能性
CBAMはEU単独での取り組みで始まりましたが、今後の課題として国際的な連携が挙げられます。カーボンプライシングを全球規模で適用する仕組みを作るためには、主要貿易国や経済圏の協調が不可欠です。例えば、日本、中国、アメリカなどの主要輸出国がこの制度にどう対応するかが、重要なポイントとなります。
また、CBAMの現在の対象製品以外にも範囲を拡大することが議論されており、仮に他の製品やセクターへ適用される場合、その影響範囲はさらに広がり、世界の貿易ルールや経済活動に持続可能性への圧力を与えることになります。
今後もCBAMが環境政策と貿易政策の両観点から進化していくことが予測されます。
まとめ
今後、CBAMの本格適用が進むにつれて、制度の詳細や関連規則がさらに明確化されるでしょう。それに伴い、各国企業、特に輸出に関連する事業者は、炭素コストへの対応を戦略的に進める必要があります。CBAMは単なる貿易制度ではなく、地球規模のGHG削減を目指す環境政策であり、すべての利害関係者がその意義と具体的影響について深く理解することが求められます。
日本企業においても、CBAM規制に対応するにあたり、対象製品の見直しや輸出戦略の再構築、GHG排出量削減への取り組みが鍵となるでしょう。
CBAMがもたらす環境改善への寄与を最大限に活かすためには、企業個々の適応とともに、日本全体としての国際的な連携強化が必要となります。
CBAMの制度理解から実務対応、ツール導入まで、企業の状況に応じた支援を行っています。貴社の体制や進捗状況に合わせてご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
〈参照元〉※1 EU の炭素国境調整メカニズム(CBAM)規則の解説 https://criepi.denken.or.jp/jp/serc/research/files/290/pdf/23002dp.pdf
※2 Fit for 55
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fit-for-55/※3 経済産業省|炭素国境調整措置https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/cbam/cbam.html
※4 JETRO|EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)に備えるhttps://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0801/a48cfe7206a68970.html
※5 経済産業省|CBAMの論点と対応状況https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/cbam/pdf/001_05_00.pdf
※6 JETRO|CBAM移行期間が開始、EU域内の輸入事業者以外も対策は必要https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/10/bd8af91b78ab2a3f.html
※7 JETRO|EU 炭素国境調整メカニズム (CBAM)の解説(基礎編)https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/b56f3df1fcebeecd/20230036.pdf
※8-1 A Clean Industrial Deal for competitiveness and decarbonisation in the EU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_550※8-2 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021PC0564※8-3 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/7807ca8b-10ce-4ee2-9c11-357afe163190_en※8-4 NRI|Equilibrium carbon price for future carbon pricing in Japan
https://www.nri.com/en/knowledge/publication/lakyara_202405/files/000026975.pdfAnnexes to the CBAM Implementing Regulation for the transitional phase
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_228_R_0006#d1e32-113-1