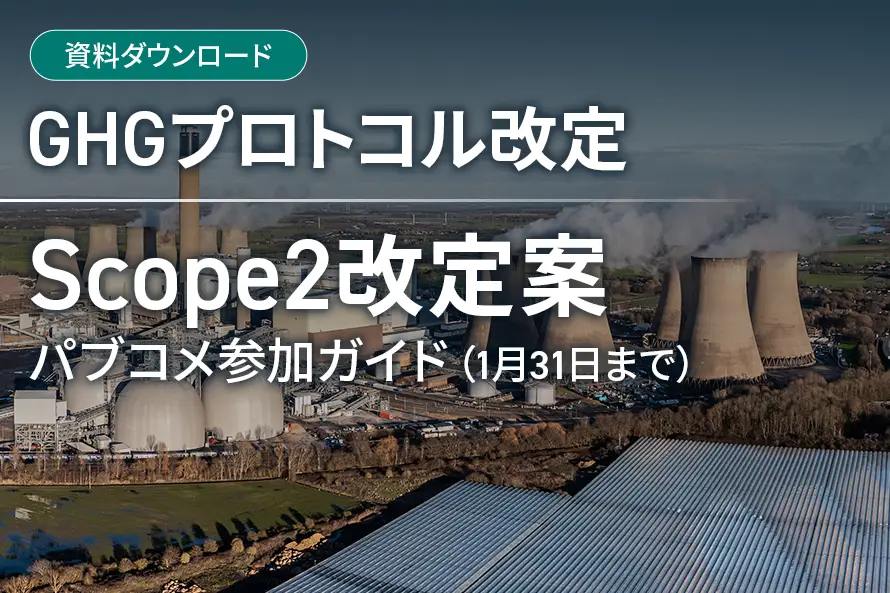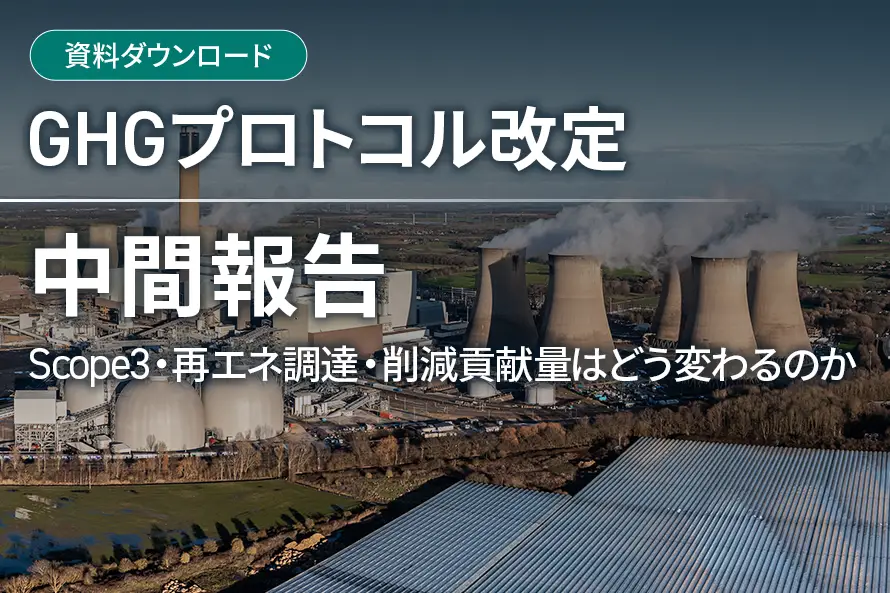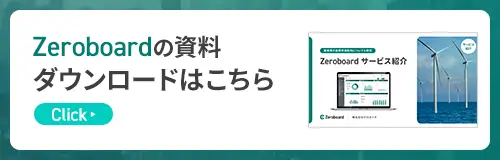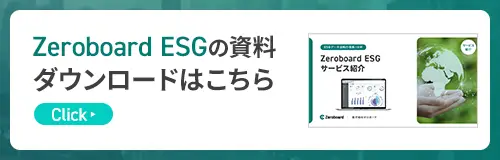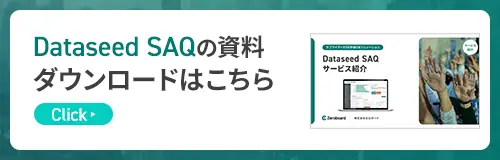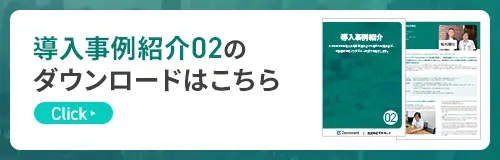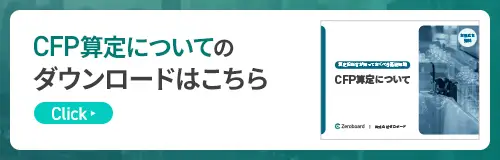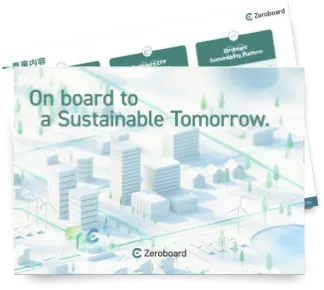TCFDとは?わかりやすく解説!開示項目やシナリオ分析について

現在、企業や投資家の間で気候変動のリスクや機会を認識することが重要視されています。TCFDは、企業が温室効果ガスの排出による気候関連情報を適切に開示することを提言しました。
ここでは、TCFDについて具体的な取り組みや提言内容について詳しく解説します。
TCFDとは
TCFD(Task Force on Climate related Financial Disclosure)は、気候関連財務情報開示タスクフォースの略称です。G20の要請を受け、2015年に金融安定理事会(FSB)によって設立され、2017年に自主的な情報開示のあり方に関する提言(TCFD報告書)を公表しました。
設立の背景
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、企業でも脱炭素経営、そして気候関連情報の開示が要求されるようになりました。また、気候変動や地球温暖化といった問題は、環境だけでなく企業の財務状況にも影響を与え、物理的リスク、賠償責任リスク、移行リスクの3つの経路から金融システムの安定を損なう恐れがあるとされています。
各企業が脱炭素、気候変動に対する取り組みを進める中、ESG投資額も増加傾向にあり、投資家からの注目も高まっています。
TCFDの目的
環境省では、「TCFDは、全ての企業に対し、①2℃目標等の気候シナリオを用いて、 ②自社の気候関連リスク・機会を評価し、③経営戦略・リスク管理へ 反映、④その財務上の影響を把握、開示することを求めている」*1としています。
このように、TCFDでは気候変動への取り組みや財務への影響を開示することで、投資家などが適切に投資判断を下すことを目的としているのです。
TCFDに賛同するメリット
TCFDに賛同・開示することには多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
例えば、コストとしてはリソースの負担です。気候変動リスクを踏まえた対策を常に検討する必要があり、日常業務に加えて新たな業務負担が生じる点です。また、気候シナリオを用いたリスクや機会の分析には高度な専門知識が求められるため、外部コンサルタントの支援や専門人材の確保が必要な場合もあります。
TCFDへの賛同方法
TCFDへの賛同とは、TCFDが提言する枠組みに企業や組織が支持を表明し、気候変動に関する財務情報を透明性高く開示していくことを約束することを意味します。企業はまずTCFDの提言とガイドラインを理解し、自社の業務にどのように適用できるかを評価する必要があります。その上で、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標の4つの開示項目に基づき、内部体制を整備し、気候関連リスクと機会の評価・管理・開示のプロセスを確立します。
次に、企業はTCFDの公式サイトを通じて賛同手続きを行い、基本情報や賛同声明を提出します。賛同後は、自社ウェブサイトや公式文書にTCFD支持者であることを明示し、開示の取り組みを積極的に発信することが期待されます。また、金融機関や投資家はTCFDの推奨事項を投資判断に活用し、規制当局や業界団体もその普及を促進しています。
開示項目
TCFDでは、企業が開示すべき情報を以下の4つの主要項目に分類しています。*2
ガバナンス
気候関連リスクと機会に関する企業のガバナンス体制を開示します。取締役会や経営者がどのようにリスクと機会を経営戦略に反映させるため体制作りを行っているかを示します。
戦略
企業の事業や戦略、財務に対する気候変動のリスクと機会の影響を評価し、どのように対応しているかを開示します。また、長期的なシナリオ分析を用いて、気候変動が将来の事業にどのように影響を与えるかを示すことが推奨されます。
リスク管理
気候変動に関連するリスクを識別、評価、管理するためのプロセスを開示します。組織全体のリスク管理の中に、気候関連リスクの識別・評価・管理プロセスがどのように統合されているかといった情報が求められています。
指標と目標
気候変動リスクと機会の管理に使用する指標や目標を開示します。GHG(温室効果ガス)排出量の目標設定や進捗状況の報告などが含まれます。
TCFDの重要性、メリット
TCFDに基づく情報開示を行うことは、企業に以下のような様々なメリットをもたらします。
世界的な情報開示フレームワークへの対応が可能
ESG投資を⾏う機関投資家や企業の要請に基づき質問書を送付し、企業の環境対応を評価するCDPの設問が、TCFD提言に準拠していたり、自然資本や生物多様性に関するリスクや機会についての情報開示フレームワークであるTNFDがTCFDのフレームワークを参照していたりと、多くの開示フレムワークや評価機関がTCFD提言との整合を実施しています。TCFD提言は世界における情報開示フレームワーク・評価のスタンダードになりつつあり、TCFD提言に賛同することは世界的な情報開示の推進に対応することが可能となります。
投資家からの信頼獲得
TCFDに基づいた情報開示を行うことで、企業が気候関連リスクを適切に評価・管理できていることを示すことができます。近年では、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governanve)の視点を考慮した投資手法であるESG投資が拡大しているため、投資判断を行う上での信用性が高まり、ESG投資の促進に繋がります。
社会的な信頼の獲得
気候変動や環境への対応力を示すことで、競合他社との差別化を図り、市場での競争優位性を確保できます。また、持続可能な経営が消費者や取引先からの支持を得やすくなります。TCFDに基づいた情報開示を行うことは、企業のブランドイメージ向上にも繋げることができるのです。
TCFDのシナリオ分析とは
TCFDを語るうえで欠かせないのが「シナリオ分析」です。これは、気候変動やそれに伴う事業環境の悪化といったリスクに備えるために、将来を複数のパターンで想定し、それぞれに応じた対処法を検討する手法です。具体的なシナリオをあらかじめ用意しておくことで、いざという時にスムーズな対応が可能となり、長期的に不確実性の高い気候変動リスクを経営戦略に組み込むことができます。特に、気候変動の影響を受けやすい業種にとっては、その重要性が一層高いといえるでしょう。
TCFDのシナリオ分析は、単に気候リスクを把握するだけでなく、それが企業の戦略、リスク管理、財務にどのような影響を与えるかを明らかにすることを目的としています。環境省は、シナリオ分析の手順として次のプロセスを推奨しています。
- 経営陣の理解を得て、分析体制・対象・時間軸を設定する
- 気候変動により想定されるリスクと機会を洗い出し、財務への影響と重要度を評価する
- 平均気温の上昇幅などに応じて複数のシナリオを定義する
- 各シナリオが事業や財務に及ぼす影響を分析する
- その結果を踏まえて対応策を検討する
- 最終的に分析結果や対応策を文書化し、開示する。
日本におけるTCFDの取り組み状況
日本では、多くの企業がTCFDの推奨事項に賛同し、気候関連情報の開示に取り組んでいます。2022年1月時点で、687の企業がTCFDに賛同しており、その数は増加傾向にあります。また、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)に関しても、気候変動だけでなく、自然環境全般に関するリスクと機会の開示を促進する動きがあり、日本企業にとっても重要な取り組みとなっています。これらの取り組みは、企業の持続可能性と投資家の判断材料の向上に寄与しています。


<参照元>
*1:気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の 概要資料 2021年環境省
https://www.env.go.jp/press/02_TCFDgaiyousiryou.pdf
*2:TCFDとは TCFDコンソーシアム
https://tcfd-consortium.jp/about