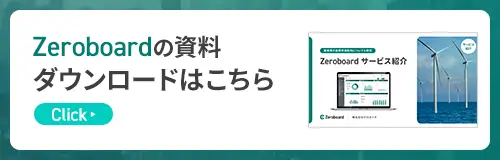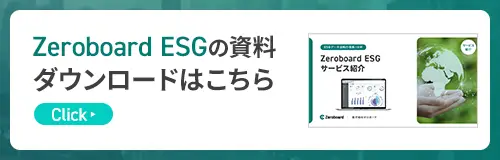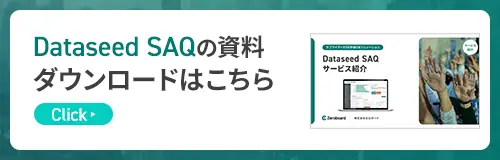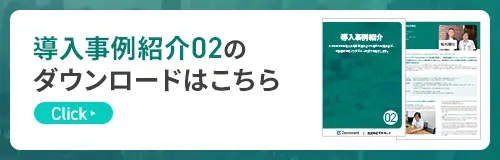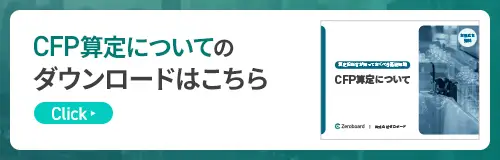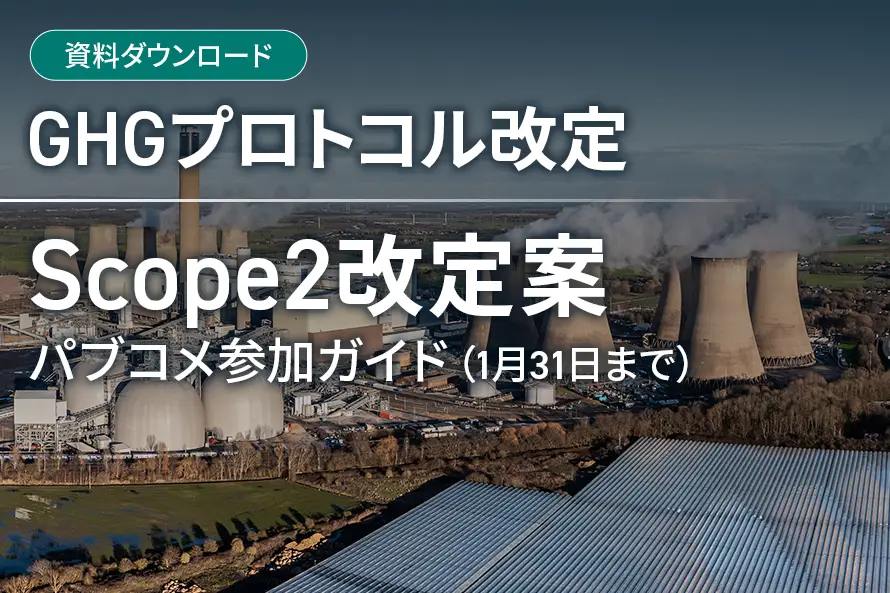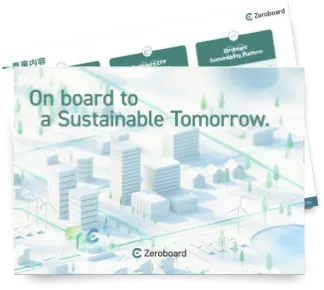Scope3(スコープ3)算定の精度を高める!一次データ活用の実務ステップ

近年、サステナビリティ開示や脱炭素経営の進展により、GHG算定の中でもScope3(サプライチェーン排出量)が注目を集めています。特に2025年3月に確定したSSBJ基準や、CDPスコアアップの観点からも、Scope3(スコープ3)の開示・精緻化は企業にとって避けて通れない課題です。
その中で重要なキーワードとなっているのが「一次データ(Primary Data)」。従来の排出係数による算定に比べ、企業やサプライヤーが実際に収集したデータを活用することで、算定精度を大きく向上させることが可能です。
本記事では、Scope3(スコープ3)算定における一次データの役割と、実務での取得・活用ステップを解説します。
Scope3(スコープ3)における一次データとは?
一次データによる算定と排出係数ベース算定の違い
Scope3とは、自社のバリューチェーン全体で発生する間接的な温室効果ガス排出量のことです。代表的なカテゴリには、購入した物品・サービス(カテゴリ1)、輸送・配送(カテゴリ4・9)、販売した製品の使用(カテゴリ11)などがあります。
Scope3算定では、「活動量 × 排出係数」の式で計算するケースが一般的です。例えば、調達金額に業界平均の排出係数を掛ける、といった手法です。しかしこれはあくまで統計値(2次データ)であり、企業ごとの努力や実態を十分に反映できません。
一次データの定義と役割
一次データとは、実際の活動に基づきサプライヤーや自社が直接収集したデータを指します。例えば、輸送に使った燃料消費量や、調達先の工場で使用した電力データなどが該当します。これを活用することで、業界平均ではなく自社サプライチェーンのリアルな排出量を算定できるのです。
なぜ一次データが重要なのか
脱炭素取り組みの排出量算定への反映
排出係数ベースの算定では、削減努力をしても数値に反映されにくい問題があります。一方、一次データを活用すれば、効率的な物流や再エネ利用などの施策が算定結果に直接表れます。また、サプライヤーの削減努力も自社の算定結果に反映することができます。
SSBJ・CDPなど制度・評価への影響
SSBJ基準(2025年3月確定)※1では、Scope3の開示が有価証券報告書に求められるようになりました。一次データを活用することで、開示内容の信頼性が高まり、第三者保証への対応もスムーズになります。
CDPスコアでも、一次データの利用は評価項目に含まれており、スコア向上の近道になります。※2
※1_SSBJ基準が確定 -完全版!サステナ開示義務の詳細と対応ポイントを徹底解説
※2_CDPで求められているScope3における一次データが占める割合は?
Scope3(スコープ3)算定における一次データ取得ステップ
着手すべき優先カテゴリ
Scope3の15カテゴリすべてで一次データを収集するのは現実的ではありません。まずは排出量が大きいカテゴリから着手することを推奨いたします。業種にもよりますが、例えば下記のようなカテゴリが大きい例が良く見られます。
- カテゴリ1:購入した物品・サービス
- カテゴリ4:輸送・配送
- カテゴリ11:販売した製品の使用
カテゴリ1・4は製造業一般で大きな値となることが、また、カテゴリ11は自動車や電気製品、建築などで大きくなる例が多くみられます。
収集フローと関係部門
1.対象カテゴリを選定
2.必要なデータを定義(例:燃料使用量、電力消費量、原材料重量など)
3.サプライヤー対象の優先順位づけ
全サプライヤーを一度に対象とするのは非現実的です。まずは取引額上位○○社などや排出量の多い主要取引先など、優先度の高いサプライヤーに絞って開始するのが効果的です。段階的に範囲を広げることで、負担を抑えつつデータ精度を高められます。
4.社内調整:調達部門・物流部門や営業・販売部門との役割分担
一次データ収集を進める際には、関係部門との調整が欠かせません。カテゴリ1・4を対象とする場合は調達部門・物流部門が中心となりますが、カテゴリ11(販売製品の使用)が大きな業種では、営業・販売部門も関与が必要です。
5.外部協力:サプライヤーや物流事業者からのデータ収集
この流れを一度整備すると、翌年以降の算定効率が大幅に改善します。
そして、一次データの収集では、サプライヤーへの協力依頼が不可欠です。しかし、この協力を得ることは非常に重要である一方、多くの企業が躓くポイントでもあります。次章では、その具体的な方法を解説します。
サプライヤーからデータを集める方法
SAQ(サステナブル調達アンケート)の活用
近年多くの企業が導入しているのが、サステナビリティ調達質問票(SAQ)です。排出量データだけでなく、人権・環境対応の情報も同時に集められるため効率的です。
インセンティブ設計と負担軽減
サプライヤーにとっては、データ提供は負担になります。そのため、フォーマットを簡潔にする、提供したデータをレポート化してフィードバックするなどの工夫が効果的です。
調達方針・ガイドラインへの明記
調達方針やガイドラインに「データ提供を求める」旨を明記することで、取引基準の一部として位置づけられ、継続的なデータ収集が可能になります。これにより、依頼ベースからガバナンスに基づく仕組みへと移行でき、算定プロセス全体の信頼性も高まります。
ツール・システム導入による効率化
スプレッドシートベースの収集では限界があります。GHG算定ツールや専用システムを活用すれば、データ収集・検証・統合を自動化でき、ミスや属人化も防げます。
サプライヤー向け勉強会の実施
サプライヤーに一次データ提供をお願いする際は、単に「データ提出を依頼する」だけでは協力を得にくいのが現実です。なぜScope3算定が必要なのか、サプライヤー側にどんなメリットがあるのかを理解してもらうことが欠かせません。
勉強会や説明会の場を設けることで、以下の効果が期待できます。
- 開示要請や国際的動向を背景に、Scope3の重要性を理解してもらえる
- サプライヤー自身のGHG算定レベルが上がり、ESG評価や取引先との関係強化につながる
- 「データ提供=自社の企業価値向上にも資する」と納得してもらえる
このように「協力依頼」から「共に価値を高める取り組み」へと発想を転換させることで、一次データ収集がスムーズに進むと同時に、サプライチェーン全体の脱炭素化を後押しできます。
一次データ活用で得られるメリット
一次データを取り入れ、Scope3算定の精度が上がると、どのような実務的なメリットがあるのでしょうか?
以下に具体的な観点を交えてご紹介します。
数値の変化を実感できる
一次データを取り入れると、従来の推計値と比べて数値が数%〜十数%程度下がるケースが少なくありません。これは、業界平均の排出係数では反映されない企業独自の改善努力(燃費効率の向上、再エネ利用など)が、実測データにはきちんと表れるからです。
削減余地が見える化される
実測に基づいたデータが揃うと、業界平均では隠れていた改善ポイントが明らかになります。たとえば「輸送手段別の排出効率」や「原材料ごとの排出強度」が見えるようになり、削減施策の優先順位づけが容易になります。
開示と社内活用の信頼性が向上する
一次データを基盤にしたScope3算定は、SSBJ基準に基づく有価証券報告書の開示や、CDPスコア評価の場面で高い信頼性を担保できます。さらに、算定結果を社内の経営判断や投資意思決定にも活かせるため、単なる制度対応を超えて経営戦略の材料として活用できるようになります。
このように、一次データを活用することで、Scope3算定は「精度が高まる」だけでなく、数値変化の実感・削減施策の特定・信頼性ある開示・戦略的な社内活用といった具体的成果へとつながります。つまり、一次データの取得と活用は、制度対応を超えて企業価値向上の基盤をつくるステップと言えるでしょう。
まとめと次のステップ:実務から経営活用へ
本記事では、「サプライチェーンに向けた一次データ収集を行う際の実務ステップ」に焦点を置いて解説してきました。Scope3の一次データは、「制度対応のための数字」ではなく、脱炭素の推進や経営判断を動かす武器になり得ます。
そのためには、効率的なデータ収集の仕組みづくりと、全社的なESGデータの一元管理を同時に進めることが重要です。
企業がこうした取り組みを実効性のあるものとするために、ゼロボードでは以下のサービスをご用意しています。詳細は各サービスページをご覧ください。
Zeroboard:サプライチェーン全体でガバナンスの効いた環境データの一元管理を可能にします。
Dataseed SAQ:バイヤーからサプライヤーに対するSAQ(Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート)の収集・管理を効率化するクラウドサービスです。
Zeroboard ESG:欧州CSRD、有価証券報告書・SSBJなどの国内外のサステナビリティ法定開示に耐えうるESGデータ収集・分析を行うことができます。