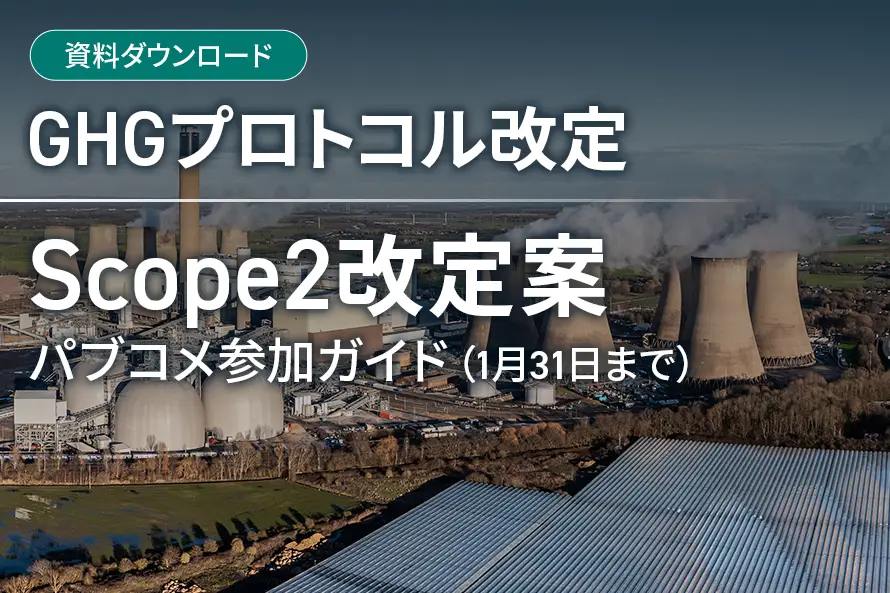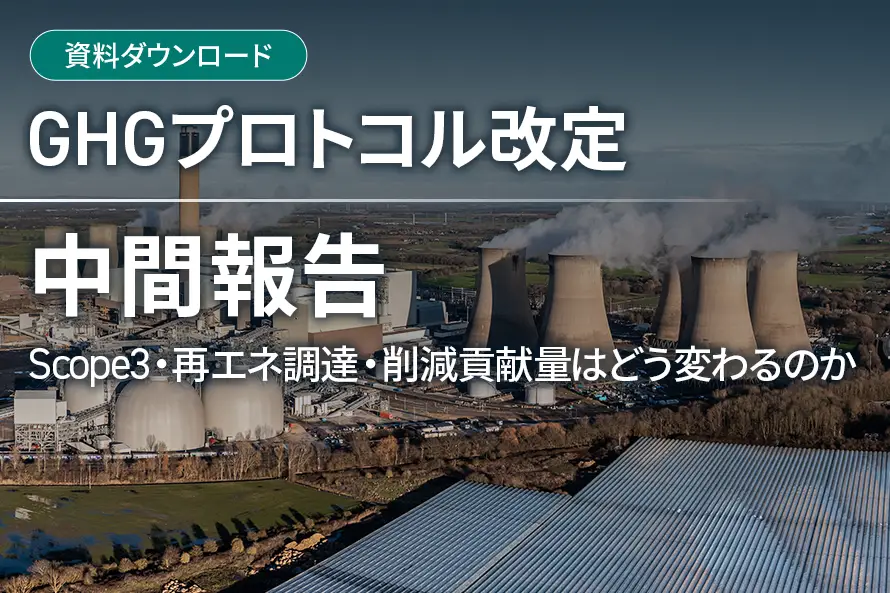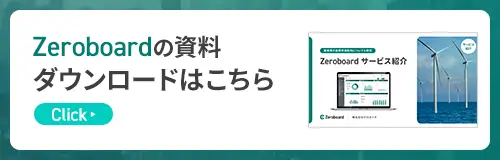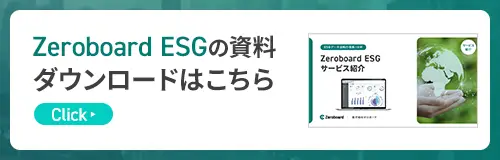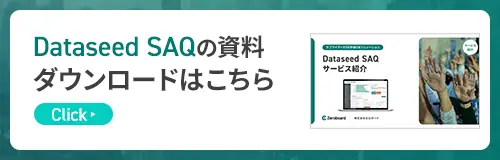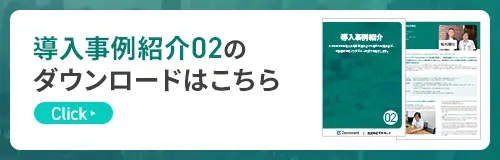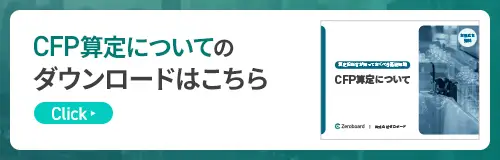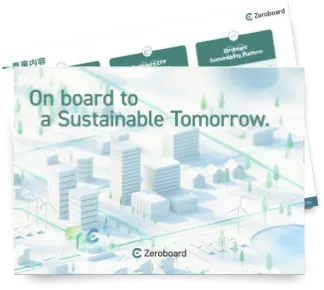カーボンフットプリント(CFP)とは?算定・計算方法を簡単に解説

カーボンフットプリント(CFP)とは、製品やサービスのライフサイクル全体で排出される温室効果ガス(GHG)をCO2に換算して“見える化”する取り組みです。
脱炭素経営やサプライチェーン全体の排出量開示が求められる中、カーボンフットプリント(CFP)は企業にとって重要な指標として注目を集めています。
本記事では、カーボンフットプリント(CFP)の基本的な考え方から、算定方法、企業の取り組み事例までをわかりやすく解説します。
初めてCFPに取り組む担当者の方でも、実務の第一歩がイメージできる内容になっています。
カーボンフットプリント(CFP)とは
カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Products)とは、製品やサービスが生産・輸送・使用・廃棄に至るまでの各段階で排出する温室効果ガス(GHG)を、二酸化炭素(CO2)に換算して“見える化”する仕組みです。
原材料の調達から製造、輸送、使用、廃棄に至るまでのすべての工程が対象となり、製品1単位あたりの排出量として数値化されます。※1
CFPは、製品ごとの温室効果ガス排出量を定量的に把握するための指標であり、企業の脱炭素経営や製品戦略、さらには消費者の選択行動においても活用されるようになっています。
※1:中間製品等の場合には、製品の原材料調達から出荷までという場合もあります。
カーボンフットプリント(CFP)が注目される理由と企業にとってのメリット
脱炭素社会への移行が世界的に加速する中で、製品単位で排出量を明示するカーボンフットプリント(CFP)の重要性が高まっています。
製造業や流通業をはじめとする企業にとって、製品のどの工程でどれだけ温室効果ガスが排出されているのかを把握することは、排出削減のための最初のステップとなります。
また、顧客や取引先からのESG要請に応える手段としても、カーボンフットプリント(CFP)の算定・開示が活用される場面が増えています。特にBtoB取引においては、一部の業界でグリーン調達の基準や入札要件としてカーボンフットプリント(CFP)の提出や算定実施を求める動きがみられるようになっています。例えば、電機・自動車など環境配慮設計が重視される業界では、部材レベルでのCFP算定を要求する企業も増えつつあります。
一方で、カーボンフットプリント(CFP)は消費者にとっても、環境に配慮した製品を選ぶための判断材料の一つとなります。商品のCO2排出量が表示されることで、環境負荷の低い商品を選ぶ意識が高まり、市場全体の行動変容にもつながります。
このようにカーボンフットプリント(CFP)は、企業と消費者の両方にとって価値のある情報基盤として位置づけられており、今後さらに幅広い分野での活用が期待されています。
カーボンフットプリント(CFP)算定の基礎知識|LCAをベースに算定の仕組みを理解する
CFPは、ISO 14067などの国際規格に基づき、GHG排出量を製品単位で見える化する取り組みです。その中核となるのが、ライフサイクルアセスメント(LCA)です。ここでは、カーボンフットプリント(CFP)算定の基本構造と、実務で参考となる国内のガイドラインを紹介します。
LCA(ライフサイクルアセスメント)とは
LCA(Life Cycle Assessment)は、製品やサービスのライフサイクル全体を通じて、環境負荷を定量的に評価する手法です。
原材料の採取から製造、輸送、使用、廃棄・リサイクルまでを網羅し、「各工程での活動量 × 排出係数」を積み上げてCO2排出量を算出します。
カーボンフットプリント(CFP)はこのLCAの枠組みをもとに、温室効果ガス排出量に対象を絞って計算します。具体的には、次のような構成になります。
- 原材料の重量や輸送距離などの活動量データを収集し
- それぞれに対応する排出係数をかけ合わせ
- 製品1単位あたりの総排出量をCO2換算で導出
こうした計算には、社内の実測データ(一次データ)や、政府・業界等が提供するデータベース(二次データ)を組み合わせて使用するのが一般的です。
実務では「経産省ガイドライン・実践ガイド」が参考に
カーボンフットプリント(CFP)の算定は、企業が独自に自由な方法で行ってよいものではなく、一定の手順や考え方に則って進めることが重要です。
その際に実務の参考となるのが、経済産業省および環境省(2023年5月)が公開している「カーボンフットプリントガイドライン」および「カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP実践ガイド」です。
これらは、カーボンフットプリント(CFP)算定の基本的な流れや考え方を整理したもので、
- 算定対象や範囲の定め方
- データ収集時のポイントや注意点
- 製品構造に応じた柔軟な設計の考え方
などが解説されています。
とくに「実践ガイド」は、初めてカーボンフットプリント(CFP)に取り組む企業でもイメージしやすいよう、より実務的なフローや記載例が紹介されており、導入時の道しるべになります。
【参考リンク】
経済産業省・環境省|カーボンフットプリント ガイドライン(2023年3月)
経済産業省・環境省|カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP実践ガイド(2025年3月)
次章では、これらのガイドラインの考え方を踏まえつつ、実務で押さえておくべきカーボンフットプリント(CFP)算定の基本ステップを順を追ってご紹介します。
カーボンフットプリント(CFP)算定の流れをわかりやすく解説
カーボンフットプリント(CFP)の算定プロセスは、実際に「各工程での活動量 × 排出係数」を積み上げる作業に至るまでに、いくつもの重要な準備ステップを伴います。
算定の目的や対象製品の整理、ライフサイクルのどこまでを算定対象とするかの範囲設定、必要なデータの整備といった前段階には一定の専門知識が求められ、準備段階でつまずく企業も少なくありません。
また、算定が終わったあとも、結果の検証や報告方法、社内での活用方針をどう設計するかといった論点も見逃せません。
この章では、カーボンフットプリント(CFP)を正確かつ実務的に算定するために押さえておきたい5つの基本ステップを、順を追って解説します。
(1)目的と算定方針を明確にする
なぜカーボンフットプリント(CFP)を算定するのか?どの製品を対象とし、誰がプロジェクトを主導するのか?
こうした基本的な方針を明確にしておくことが、カーボンフットプリント(CFP)算定の出発点となります。
たとえば、「顧客からの要請に応えるため」「製品開発に活かすため」「社内の脱炭素施策の一環として」など、目的によって必要な精度や開示範囲は異なります。
算定のゴールが曖昧なまま進めてしまうと、途中でデータの取り直しや手戻りが発生するリスクもあるため、最初に「なぜ・何のためにやるのか」を明文化することが重要です。
あわせて、対象とする製品群(1製品/シリーズ全体/部材単位など)や、社内の推進体制(環境部門、製造部門、サステナビリティ担当など)も整理しておきましょう。どの製品を優先的に算定するかという判断は、次の工程である算定範囲の設定にも大きく影響します。
特に複数部門にまたがるデータ収集やレビューが必要になるため、算定実務部門と関係部署の役割分担を早めに調整しておくことが、プロジェクト全体の成功を左右します。
(2)対象製品とライフサイクルの範囲を定める
カーボンフットプリント(CFP)を算定する際には、どの製品を対象にするのか、そしてライフサイクルのどこまでを算定範囲とするのかを明確にする必要があります。
この工程を曖昧にしたまま進めてしまうと、後工程でのデータ不足や、関係者間の認識ずれが発生しやすくなります。
製品の選定では、「主力製品から始める」「CO2排出量が多そうな製品を優先する」「顧客要請が来ている製品を対象とする」など、社内外の状況に応じた判断が必要です。
製品構成やサプライチェーンの複雑さも、データ収集の難易度に影響します。
また、ライフサイクル範囲の設定では、以下のような選択肢があります:
- Cradle to Gate(ゆりかごから出荷まで):原材料の採取から製品の出荷時点まで
- Cradle to Grave(ゆりかごから墓場まで):原材料採取から製品の使用、廃棄・リサイクルまでの全工程
一般的に、製品の種類や算定の目的に応じて範囲は変わります。たとえば、部品メーカーであれば納品時点の「Gate」までが対象となることが多い一方で、消費財など最終製品を扱う場合は、使用・廃棄まで含めた「Grave」が求められることが一般的です。
どの範囲を採用するかは、商習慣や原材料の仕入れ方法や工期など業界特有の慣習、顧客要請、自社の経営戦略との整合性を踏まえて検討することが大切です。
(3)排出量の計算ロジックを設計する
対象製品と算定範囲が決まったら、いよいよ排出量を計算するためのロジックを設計していきます。
カーボンフットプリント(CFP)の算定は、基本的に「活動量 × 排出係数」というシンプルな構造に基づいていますが、実際にはその前提となる原材料や部品レベルへの分解や、活動データの整理、排出係数の選定が重要になります。
活動量とは、たとえば「使用した原材料の重量」「電力使用量」「輸送距離」「廃棄物の量」など、排出につながる物理的なデータを指します。
これに対して排出係数は、「その活動1単位あたりにどれだけのCO₂が排出されるか」を示す数値で、対象となる活動に対して適切な値を選定する必要があります。
カーボンフットプリント(CFP)算定に用いるデータは、活動量・排出係数のいずれにおいても、次のように一次データと二次データに分類されます。
それぞれの具体的なデータのイメージは、以下の通りです:
- 一次データ:自社の実測値や、原材料の供給元(仕入先・商社など)から直接入手した情報
(例:工場の電力使用量、輸送距離、原材料の組成情報、サプライヤーから取得した排出係数など) - 二次データ:政府機関や業界団体が提供する統計値や、LCAデータベースに掲載された一般的な排出係数・使用パターン(製品の使用期間・稼働頻度などの標準的な前提条件)など
(例:排出原単位データベース、AIST-IDEA、ecoinventなど)
関連記事:
一般に、一次データの方が精度が高く、実態に即した算定が可能ですが、すべての工程で一次データを揃えるのは現実的に難しい場合もあります。
そのため、算定の目的や必要とされる精度に応じて、一次・二次データを適切に組み合わせて活用したり、明らかに影響が小さい場合はルールに沿ってカットオフしたりすることが実務上のポイントとなります。
また、LCA(ライフサイクルアセスメント)に基づき、どの工程を対象とし、どのようなデータを使って排出量を積み上げるかを正しく設計することで、排出量の再現性や算定結果の信頼性を担保することができます。
このように、カーボンフットプリント(CFP)算定は単なる「掛け算」ではなく、データの精度・整合性・出所の明確さまで含めて設計することが極めて重要です。
(4)排出量の積算ステップを製品ごとに設計する
この章では、「活動量 × 排出係数」という基本構造を、実際の製品やサービスの特性に応じてどのように組み立てていくかを解説していきます。
製品構成の複雑さやデータの取りやすさに応じて、算定方法の設計には工夫が必要です。
単一製品なのか、複数の構成部材からなる製品か、用途ごとにバリエーションがあるのか、構造によって最適な設計は異なります。
たとえば:
- 単純な単一製品 → 原材料投入量や製造工程のエネルギー使用量から直接積み上げ
- 複数部品の組み合わせ製品 → 各部材ごとに算定し、組み合わせて合算
- 製品群(複数サイズや仕様)→ 主要モデルの代表値化、または販売量等での重付値
このように、どのレベルで分解・集計するかの設計が極めて重要です。
構成が複雑な場合やデータ収集が難しい場合には、「製品群」や「代表モデル」による近似アプローチに加えて、二次データの活用やモデル化といった工数を抑える算定方法も現実的な選択肢です。
また、委託製造や複数拠点で生産している製品では、どこまで実態に即すか/どの程度一般化するかという線引きもポイントになります。
「一律に正確性を目指す」よりも、目的に沿って合理的な粒度で算定手順を設計することが、継続性あるカーボンフットプリント(CFP)算定には欠かせません。
(5)算定結果の検証と開示対応
算定が完了したら、その結果を活用・社外開示する前に、「その算定が妥当であるか」を確認するステップが必要です。
特に、顧客や取引先からの要請や外部公開を前提とする場合、社内チェックに加えて外部の専門家による確認を検討する企業も増えています。
カーボンフットプリント(CFP)算定に対する評価の方法には、大きく2つのアプローチがあります:
- クリティカルレビュー(Critical Review)
ISO 14040/44やISO 14067の要求事項に基づき、「LCAの枠組みに沿った方法論で算定されているか」適合性を確認するもので、主に製品やサービス単位のCFPスタディが対象となります。 - 第三者検証(Verification)
経済産業省のカーボンフットプリント(CFP)ガイドラインなどの算定マニュアルに従って「実際の計算内容やデータの妥当性、プロセスの整合性」を検証するもので、製品単位で外部の検証機関によるレビューを受ける形式です。
どちらを選択すべきかは、社内にカーボンフットプリント(CFP)やLCAの知見がどの程度あるか、納入先から何を求められているか、またどこまで外部に説明責任を果たす必要があるかといった状況によって異なります。
たとえば、ISOに準拠したLCA算定体制が構築され、専門スキルを持った人材が育成されている企業であれば、業界のガイドライン等に従い、自社で手順を設計したうえで、実際の計算結果に対する第三者検証(Verification)を受けることで、正確性を対外的に担保するケースが見られます。
一方で、初めてカーボンフットプリント(CFP)に取り組む企業や、LCAのプロセス設計に不安がある場合には、方法論そのものがISOの考え方に沿っているかを確認する「クリティカルレビュー(Critical Review)」を検討することもあります。
また、算定結果を社外に公表する場合、どのような媒体・文脈で開示するかも重要です。
たとえば:
- 製品パッケージにCFP値を表示(消費者向け)
- 顧客企業のScope3報告に活用(取引先向け)
- サステナビリティレポートやTCFD開示に記載(投資家向け)
開示する際は、カーボンフットプリント(CFP)の値そのものに加えて、前提条件・算定範囲・使用した係数の情報もセットで記載することが、比較可能性を保つ上で欠かせません。
なお、次章では、経産省のガイドラインに沿ってCFP算定を行い、検証を実施した企業の具体事例をご紹介します。
企業によるカーボンフットプリント(CFP)算定の事例
実際にカーボンフットプリント(CFP)を算定・公表した企業の事例を見てみましょう。ここでは、ゼロボードと共にカーボンフットプリント(CFP)算定に取り組んだ岩谷産業株式会社の取り組みを紹介します。
岩谷産業では、主力製品の一つである「イワタニカセットガス(オレンジ)」について、製品1本あたりの原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体を対象にCO₂排出量を算定しました。
このCFPは、製造時のエネルギー起因の排出量にとどまらず、購入した原材料、製品の輸送、廃棄に至るまでの排出を網羅しており、以下のような特徴があります:
- ISO 14067や経済産業省・環境省のガイドラインに準拠した算定手順
- 算定結果は第三者検証機関(ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社)による審査を受けている 。
- 算定結果を社外に開示し、ステークホルダーとの信頼関係強化や社内の環境意識向上につなげている
カーボンフットプリント(CFP)の公表は、製品の環境価値を可視化するだけでなく、従業員の意識変革やサプライチェーン全体の脱炭素への波及効果にもつながる実践例です。
関連記事:【導入事例】看板商品「イワタニカセットガス(オレンジ)」のCFP算定を実施。算定と公表が社内外にもたらした効果とは?
まとめ
カーボンフットプリント(CFP)は、製品やサービスのライフサイクル全体における温室効果ガス排出量を「見える化」するための重要な手法です。単なるCO₂の算定にとどまらず、製造や輸送など各工程における温室効果ガス排出量を明らかにし、削減すべきポイントを定量的に把握することが可能になります。
企業にとってカーボンフットプリント(CFP)の活用は、次のようなメリットがあります。
- 自社製品の温室効果ガス排出量を客観的に把握できる
- 取引先からの要求・開示義務への対応が可能になる
- サプライチェーン全体の脱炭素戦略に貢献できる
一方で、正確な算定には多くの準備や検証が求められるため、専門知識と適切なツールの導入がカギとなります。
カーボンフットプリント(CFP)算定支援サービスのご案内
Zeroboardではカーボンフットプリント(CFP)の算定支援や専用ツールの提供を通じて、製品単位・サービス単位のCO₂排出量の可視化と削減をサポートしています。
Zeroboardでは、LCAやサステナビリティ情報開示に精通した専門コンサルタントが在籍しており、算定設計から第三者検証対応まで、実務レベルで支援いたします。
「自社製品のCO₂排出量を見える化したい」「顧客や親会社からカーボンフットプリント(CFP)開示を求められている」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。